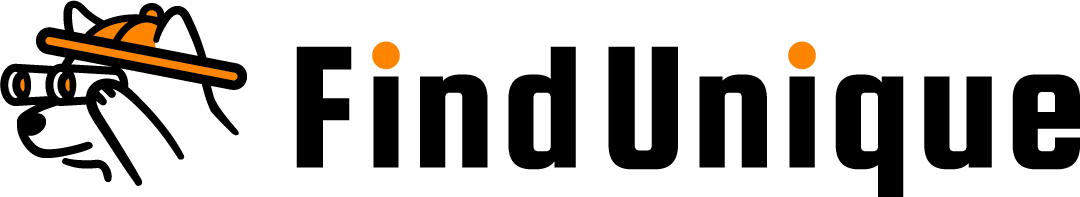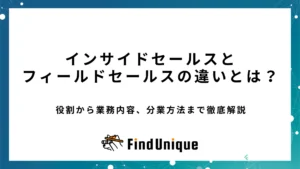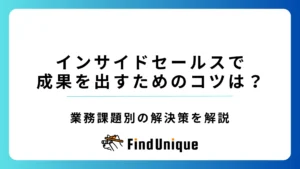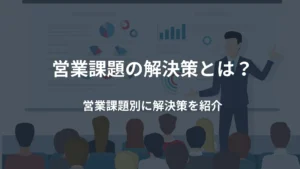インサイドセールスの立ち上げ方法とは?失敗しないための組織構築の手順を解説
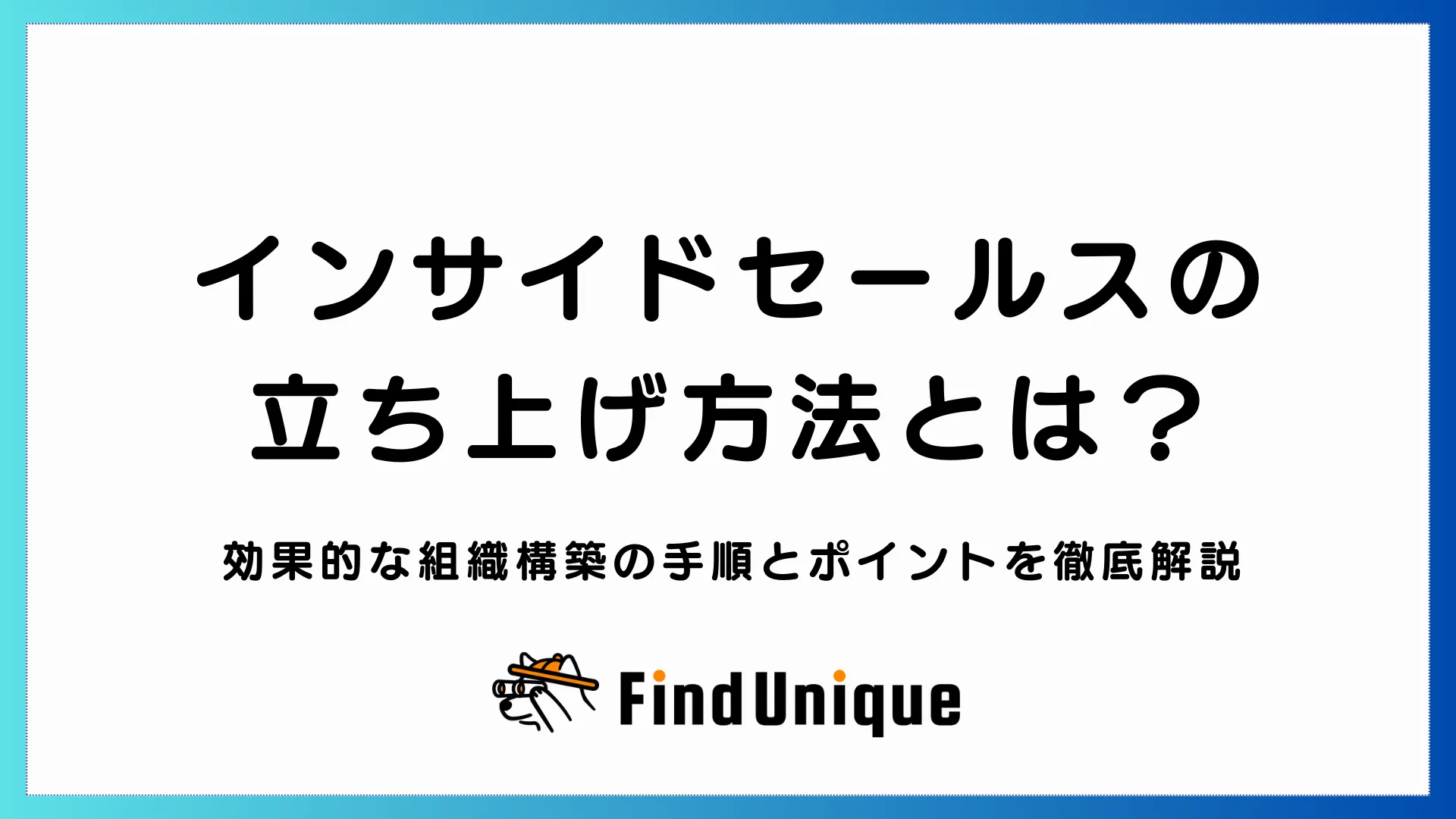
資料請求のフォロー漏れ対策や、セミナー・展示会のフォロー体制の強化を目的に、インサイドセールスを立ち上げる企業が増えております。しかし、インサイドセールスチームを立ち上げようと思っても、どういった流れで進めたら良いかご存じでしょうか?
インサイドセールスの役割の範囲を明確にせずに立ち上げると、想定していた効果が出ずに失敗してしまうことも少なくありません。本記事では、インサイドセールスの立ち上げの手順と確認すべきポイントについて解説いたします。
インサイドセールスとは?
インサイドセールスは、主に電話やメール、オンラインツールを活用して社内から行う営業活動を指します。顧客との直接的な対面を必要とせず、効率的にリードを獲得し、商談を進めることができるのが特徴です。その主な目的は、新規リードの獲得と育成、既存顧客のフォローアップと関係強化、商談の創出と初期段階での対応、そしてフィールドセールスのサポートと効率化にあります。
インサイドセールスを導入することで、企業はコスト削減や営業プロセスの効率化を実現できます。さらに、データに基づいた戦略立案が可能となり、より効果的な営業活動を展開できるでしょう。
インサイドセールスの概要については以下の記事で詳しく解説しているので、ご参照ください。
【関連記事】:インサイドセールスとは?業務内容・メリット・立ち上げ方を徹底解説
インサイドセールスの立ち上げ手順
インサイドセールスの立ち上げは、段階的に進めていくことが重要です。
1.施策実施前に準備を徹底する
インサイドセールスの立ち上げにあたっては、まず業界や自社商材について分析するところから始めます。この段階で重要なのは、自社商材のコアコンピタンスを把握し、カスタマージャーニーを把握することです。
自社の課題を抽出する
インサイドセールスを導入するためにも、まず実施すべきなのが自社の課題を明確にすることです。「フィールドセールスが訪問に時間を取られすぎている」「リードの商談化率が低い」「ターゲット層との接点が少ない」などの問題点を洗い出していきましょう。
ただし、営業部門だけで課題を抽出するのではなく、マーケティングやカスタマーサクセス部門とも連携してください。各部門と連携することで、よりボトルネックの要因を探りやすくなります。
自社商材の強みを洗い出す
自社の商品やサービスの強みと弱みを分析し、顧客にとっての価値提案を明確にすることが重要です。例えば、「他社にはない独自技術」や「圧倒的なコストパフォーマンス」など、自社商材の特徴を明確に把握しましょう。これにより、インサイドセールスのトーク内容や提案の方向性が定まり、効果的なアプローチが可能となります。
自社におけるインサイドセールスの目的を明確する
インサイドセールスの目的は、企業によって異なるため、自社のケースでの目的を明確にしましょう。例えば、「新規リードの商談化率向上」「休眠リードの再活性化」「既存顧客のクロスセル・アップセル支援」など、何らかの目的があるはずです。
目的が曖昧なままでは、営業チームが正しいKPIを設定できず、適切なアクションが取れなくなります。導入目的を社内で共有し、各部署と連携しながらインサイドセールスの位置付けを決定しましょう。
2.カスタマージャーニーを把握する
第2ステップでは、「カスタマージャーニーの把握」を進めていきます。インサイドセールスの立ち上げをスムーズに進めるためにも、以下を参考にしてみてください。
顧客の購買意思決定プロセスを探る
顧客の購買意思決定プロセスを探っていくことで、必然的にカスタマージャーニーの把握につながります。
例えば、「情報収集段階」「比較検討段階」「意思決定段階」など、顧客がどのような段階を経て購買に至るのかを明確にします。そして、それぞれの段階で顧客が求める情報や支援を把握し、適切なアプローチ方法を設計しましょう。
意思決定プロセスごとに必要なアプローチを探る
カスタマージャーニーを把握するためにも、意思決定プロセスごとの適切なアプローチを考えることが重要です。
認知された段階のフェーズであれば、業界のトレンドや導入事例などの情報提供が有効であると考えられるでしょう。しかし、比較検討の段階にある層に対しては、競合よりも優位である点をアピールする必要があります。
また、顧客がどのフェーズにいるのかを見極めるために、ヒアリングの質問や顧客の行動データも活用していきましょう。
3.ターゲット企業について情報収集する
次に重要なのは、ターゲットの選定と営業手法の選択が鍵となります。どのように、ターゲット企業の情報収集を進めていけばいいのか、以下から見ていきましょう。
理想的なペルソナを設定する
ターゲット企業に関する情報収集のために、自社が理想としているペルソナを設定してみましょう。
理想のペルソナが明確になれば、「どのような企業が競合になりそうか」を判断しやすくなります。
具体的には、「従業員数100人程度の製造業」や「年商10億円以上のIT企業」など、具体的な基準を設定しましょう。これにより、効率的なアプローチが可能となり、成約率の向上につながるでしょう。
ターゲット企業をリスト化及び優先順位付け
ターゲット企業をリストアップすることは、インサイドセールスの効果を高めるためにも、必要なステップです。
業種や企業規模、地域のほか、売上規模等、あらゆる領域でセグメントし、優先順位をつけていきましょう。
とくに「成約率の高そうな企業属性」を分析できれば、より効率的なアプローチも実現しやすくなります。
ターゲット企業に適した営業手法を探る
電話、メール、ウェビナーなど、適切な手法を選定し、各手法の特性を活かした活用シーンを設計します。例えば、初期接触は電話で行い、詳細な情報提供はメールで、製品デモはウェビナーで実施するなど、段階に応じて最適な手法を組み合わせることが効果的です。
4.シナリオ設計を実施する
インサイドセールスを立ち上げるうえで、欠かせないのがシナリオ設計です。具体的に、どのように設計していくべきなのか、以下から見ていきましょう。
インサイドセールス・フィールドセールスの領域を考慮する
インサイドセールスとフィールドセールスの担当範囲を明確化し、引き継ぎポイントと基準を設定することが重要です。先述の連携の型がこちらに当たります。どのタイミングでフィールドセールスに引き継ぐかを明確化することでスムーズな連携が可能となります。
インサイドセールスの効果を最大限に引き出すには、フィールドセールスとの適切な連携が不可欠です。両者の役割を明確に分担し、それぞれの強みを活かすことで、営業活動全体の効率と効果を高めることができます。
なお、フィールドセールスとの連携には、さまざまなメリットがあります。具体的には、以下の通りです。
- フィールドセールスリソースの最適化の実現
- リードの取りこぼし(未フォローリード)を削減できる
- 営業課題の見える化
まず、フィールドセールスのリソース最適化が実現できます。インサイドセールスが初期対応や基礎的な情報収集を担当することで、フィールドセールスは重要な商談や複雑な提案に集中できるようになります。
また、リードの取りこぼしを削減できるのも大きな利点です。インサイドセールスが継続的にフォローすることで、これまで見逃されていた潜在的な商談機会を発掘し、成約につなげられる可能性が高まります。
さらに、営業課題の可視化も進みます。インサイドセールスとフィールドセールスの連携を通じて、商談プロセスの各段階での課題や改善点が明確になり、より効果的な営業戦略の立案につながるでしょう。
ちなみに、連携の型は以下を参考にしてみてください。
インサイドセールスとフィールドセールスの連携には、主に3つの型があります。それぞれの型は、商材や業界の特性に応じて選択されます。
まず、「インサイドセールスからフィールドセールスにトスする型」は、高額で複雑なB2B向け製品やサービスに適しています。インサイドセールスが初期接触と情報収集を担当し、フィールドセールスが本格的な商談とクロージングを行います。
次に、「一部インサイドセールスがクロージングする型」は、中小規模の取引や標準化された製品・サービスに向いています。この型では、インサイドセールスが初期接触から一部のクロージングまで担当し、複雑な案件のみをフィールドセールスが担当します。
最後に、「インサイドセールスだけで完結する型」は、低価格のSaaSやオンラインサービス、高度に標準化された商品に適しています。全ての営業プロセスをインサイドセールスで完結させることができます。
これらの連携型の中から、自社の商材や顧客特性に最も適したものを選択することが重要です。適切な型を選ぶことで、効率的な営業活動と高い成果が期待できるでしょう。
なお、連携を成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。主に以下の3つです。
- しっかりリードを育成してからフィールドセールスに渡す
- 商談内容をナレッジ化しインサイドセールスに生かす
- MA/SFA/CRMツールで情報共有を徹底する
まず、しっかりとリードを育成してからフィールドセールスに渡すことが大切です。インサイドセールスが十分な情報を収集し、見込み客の状況を適切に評価した上で引き継ぐことで、フィールドセールスの効率が大幅に向上します。
次に、商談内容をナレッジ化しインサイドセールスに活かすことも重要です。フィールドセールスが得た情報やインサイトをインサイドセールスと共有することで、より効果的なアプローチやトーク内容の改善につながります。これにより、全体的な営業力の向上が期待できるでしょう。
最後に、MA/SFA/CRMツールで情報共有を徹底することが挙げられます。これらのツールを活用することで、リアルタイムでの情報共有が可能となり、インサイドセールスとフィールドセールス間のコミュニケーションがスムーズになります。結果として、顧客対応の質が向上し、成約率の向上にもつながるでしょう。
インサイドセールスとフィールドセールスの連携についても、以下の記事で詳しく解説しているので、ご参照ください。
【関連記事】インサイドセールスとフィールドセールスの違いとは?役割から業務内容、分業方法まで徹底解説
営業対象からターゲットの属性を決定する
シナリオ設定では、ターゲットの属性を正しく決定できるか否かで営業の精度に差が生じます。
ターゲットを選定する際には、以下のポイントを参考にしながら自社のケースに当てはめていきましょう。
- 企業規模:大企業・中小企業・スタートアップのどこを狙うか
- 業種・業界:IT、製造業、金融、小売業などの業界特性を考慮
- 役職・部署:決裁者なのか、現場担当者なのかを明確にする
- 課題・ニーズ:自社商材が解決できる具体的な課題を持っているか
また、ターゲット企業はランク分けして、優先順位を付けることも忘れないようにしてください。
適したアクションを起こせるような運用ルールを調整する
インサイドセールスにおいて、一貫した対応を進めるためにも、明確な運用ルールを設ける必要があります。
具体的には、初回での接触(お問い合わせ等)ではいつまでに連絡をするのか、何をヒアリングするのか、などは最低限必要なルールです。
また、フォローアップに関するルールや、商談化における判断基準等も明確にしておくと、商談の時間や手間を最小限にしながら、効率の良い営業活動を実施しやすくなります。
情報提供のタイミング・内容・頻度を決める
インサイドセールスを経て商談を獲得するためには、情報提供のルールを明確にしておきましょう。どのようなタイミングで、何についての情報を、どの程度の頻度で発信するのかは重要です。
「認知段階」「比較検討段階」「意思決定段階」など、各段階に分けて、それぞれにどのように情報提供するのかを決定しましょう。
5.立ち上げの際にKPIを設定する
目標設定段階では、KPIの設定が重要です。どのようなKPIを設定すべきか、KPIを設定するうえで何に配慮すべきかを見ていきましょう。
量と質の観点でバランスの良いKPIに調整する
定量的指標と定性的指標の両方を設定することが大切です。例えば、以下のような指標が考えられます。
定量的指標の例:
- 架電数:100件/日
- 担当者接続数:10件/日
- 新規リード獲得数:100件/月
- 商談化率:20%
- 成約率:5%
定性的指標としては、顧客満足度や商談の質などが挙げられます。これらの指標を定期的に測定し、改善につなげていくことが重要です。
見直しやすいようなシステムも構築しておく
フィールドセールスへの引き継ぎ基準を明確化し、引き継ぎ時の情報共有フォーマットを作成します。
例えば、「予算確認済み」「決裁者とのアポイント取得済み」といった具体的な基準を設けることで、KPIと現状を比較したり、見直したりしやすくなります。
質の高いリードをフィールドセールスに引き継ぐことができるでしょう。
6.担当者を決定し教育を行う
組織編制段階では、適切な人材の選定と教育・フィードバック体制の構築が重要です。ここからは、インサイドセールスに関するチームの形成方法や担当者としておすすめの人材を解説していきます。
立ち上げ初期は少人数でチーム形成する
インサイドセールスを立ち上げるにあたって、複数人のチームを編成する際には、まずは少人数からスタートすることをおすすめします。
最初から大規模なチームで編成してしまうと、共有や連絡などのオペレーション面で混乱が生じやすいためです。試験的な導入をイメージしながら、少人数チームで形成し、様子を見ながら規模を大きくしていくことが重要です。
自社商材を熟知している人材をマネージャーに決定する
チームの形成が完了したら、マネージャーを決定します。チームの管理人として、インサイドセールスの施策を引っ張っていく存在が必要であるからです。
マネージャーとしてふさわしいのは、自社商材について熟知している人材です。自社商材について熟知している人材であれば、営業スクリプトの設計やトーク内容の調整などの際に、より良いアイデアを反映させることができるでしょう。
なるべく、現場経験が豊富な人材をマネージャーとして配置し、チームメンバーに商材に関する教育を実施することが重要です。
営業担当者を選定する
チーム形成及びマネージャーが決定したら、インサイドセールスの施策に関わる営業担当者を選定しましょう。
インサイドセールスに求められる人材像と必要なスキルを明確にし、内部異動と外部採用のバランスをもとに検討してください。
例えば、コミュニケーション力、ITリテラシー、商品知識などが重要なスキルとして挙げられるでしょう。内部異動の場合は既存の商品知識を活かせる一方、外部採用では新しい視点や経験を取り入れられるため、両者のバランスを考慮することが大切です。
教育・FB体制を構築する
効果的な初期研修プログラムを設計し、継続的なスキルアップ支援と評価フィードバック体制を構築します。
例えば、商品知識や業界動向、トーク術などの初期研修を行い、その後も定期的なロールプレイングやベストプラクティスの共有セッションを実施するといった方法が考えられます。
また、定期的な1on1ミーティングを通じて、個々の課題に対応したフィードバックを行うことも重要でしょう。
7.ツールを導入する
インサイドセールスの立ち上げに関する準備が整ったら、施策を進めていくために必要なツールを導入します。ツールを選ぶにあたって、何を基準に選定したらいいのか、以下から見ていきましょう。
複数のツールを比較検討して選定する
CRM/SFAなど必要なツールの選定基準を定め、導入スケジュールと教育計画を策定しましょう。ツール選定の際は、使いやすさ、他システムとの連携性、カスタマイズ性などを考慮しましょう。例えば、以下のような基準で選定を行うことができます。
- 操作性:直感的なUI、学習コストの低さ
- 機能性:必要な機能が揃っているか、将来的な拡張性
- 連携性:既存のシステムとの連携がスムーズか
- コスト:初期費用、運用コスト、ROIの見込み
選定後は、段階的な導入計画を立て、十分な教育期間を設けることが重要です。
長期利用を視野に入れたうえで検討する
ツールを導入する際には、長期利用を視野に入れたうえで、選ぶ製品を検討しましょう。インサイドセールスに関するツールは、大きなトラブルが生じない限り1年以上は継続して利用します。
そのため、初期のコストや使い勝手だけではなく、拡張性や他ツールとの連携のしやすさも考慮して選ばなければなりません。
すでに自社で使っているツールやシステムと照らし合わせながら、便利に使えそうな製品を探してみましょう。
8.スクリプト・マニュアル作成
ツールの導入が完了したら、実際にスクリプトやマニュアルの作成等を進めていきます。とはいえ、いざ作成を始めようにも、何から進めたら良いのかは悩みやすい部分です。ここからは、スクリプトやマニュアルの作成方法などについて解説していきます。
基本的な会話スクリプトを作成する
スクリプトを作成する際には、まずは「基本的な会話スクリプト」から作り始めていきましょう。
実際の会話を想定して、以下のように作成することが望ましいです。
【初回架電】
1.「お世話になっております。○○株式会社の△△と申します。突然のお電話、失礼いたします。今、お時間2分ほどいただけますでしょうか?」
(相手がOKなら続行、NGなら「また改めてご連絡してもよろしいでしょうか?」と聞く)
2.「簡単にご説明させていただきますが、弊社では○○を提供しており、特に△△業界の企業様にご利用いただいています。例えば、××のような問題では■%の改善を達成しています。」
(相手の興味を引けるよう、簡潔なバリュープロポジションを伝える)
3.「御社でも、○○の業務について、こういったお悩みはございませんか?」
(顧客の課題を引き出すための質問を投げかける)
上記は一例であるため、自社の製品やブランドに合わせて作成してみましょう。なお、スクリプトは、初回架電のほか、ヒアリング、商談、断られたときの対策など、さまざまなパターンを準備しておくことが重要です。
【関連記事】インサイドセールスのトークスクリプトに求める効果と作り方を解説
FAQ集や商品知識マニュアルを整備する
インサイドセールスでは、FAQ集やマニュアルなどを整備しておくと、顧客対応の際の品質を高めることが可能です。
実際、情報が何もない中でアプローチするよりも、ある程度相手に情報を提供できたほうが、導入後の状況をイメージしやすく、前向きに検討しやすくなります。
ただし、FAQは頻繁に更新し、常に新しい情報を維持できるようにしましょう。古い情報を提供すると、信頼や満足度が下がる恐れがあるため注意が必要です。
インサイドセールス立ち上げのポイント
ここでは、インサイドセールスを効果的に立ち上げるためのポイントを解説いたします。
ツールを活用する
データ分析ツールを活用して効果測定を行い、常に改善点を探ることが大切です。例えば、コール数と成約率の相関関係を分析し、最適なアプローチ回数を見出すといった具合です。また、ナレッジ管理ツールを使用して、成功事例や失敗事例を共有し、組織全体のスキルアップにつなげていきましょう。さらに、コミュニケーションツールを活用して、チーム内や他部署との情報共有を円滑に行うことも重要です。
他部署との連携を密に行う
マーケティング部門との協力体制を構築し、リードの質の向上や効果的なナーチャリングを実現しましょう。例えば、マーケティングオートメーションツールを活用して、リードスコアリングを行い、インサイドセールスの対応優先度を決定するといった連携が考えられます。
カスタマーサポート部門との情報連携も重要です。顧客の問い合わせ内容や満足度などの情報を共有することで、より適切なアプローチや提案が可能となるでしょう。
そして、先述のフィールドセールス部門との分業も忘れずに。両者が密に連携することで、商談の質と効率を高めることができます。
振り返りを行いPDCAを回す
定期的な成果レビューと課題抽出を行い、改善策を立案して迅速に実行することが重要です。例えば、月次で KPI の達成状況を確認し、未達の項目については原因分析を行い、改善策を検討・実施するといったサイクルを回しましょう。この際、チーム全体で議論を行い、現場の声を十分に反映させることが大切です。
【関連記事】インサイドセールスとテレアポの違いとは?役割・成果指標・スクリプトの違いまでを解説
インサイドセールスにおける立ち上げ事例
ここからは、インサイドセールスの立ち上げ事例についてご紹介します。実際に、国内の企業における成功事例をご紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
MAとの連携で商談数が2倍以上に増加
国内にて、認証サービスに関する事業を展開している企業がMAツールの導入に至りました。しかし、導入当初はツールを使いこなせず、成果がまったく得られなかったのです。
MAツールを活用しながら成果を出すための施策として、インサイドセールスの立ち上げを検討し、実際に準備から施策までを徹底して行いました。その結果、マーケティング部から営業部へ共有するリードの質が向上し、有効商談率が2倍以上にまで改善された事例があります。
顧客分析の徹底で商談数が2倍以上に増加
顧客分析を徹底したことで、商談数が2倍以上に増加した事例があります。
BtoBの領域で展開しているある企業が、営業リソース不足に頭を悩ませていました。マーケティング業者に相談し、顧客分析や市場調査などを実施し、ターゲットを厳選したうえでインサイドセールスを実施しました。
これにより、限られた営業リソースの中でフィールドセールスの生産性の向上を実現しました。
ホットリードに対する施策により商談化割合が40%弱まで向上
Web関連の事業を展開する特定の企業では、商談化の割合を40%弱まで向上させた成功事例があります。
もともとは、リードを獲得してもその後のアプローチが十分にできていないのが課題として挙がっていました。
案件数や案件の進捗なども社内できちんと共有・把握ができておらず、問題としてはやや深刻な状態だったのです。
しかし、インサイドセールスを導入し、ユーザーの行動履歴をもとに適切なアプローチができるようになったことで、商談化数は大幅に向上しました。
有益な商談にフォーカスした施策により受注率を向上
「商談につながっても成約まで至らない」と悩む企業では、インサイドセールスによって受注率を向上した事例が存在します。
「とりあえず話を聞いてみたい」といった声を受け、すべての相談に応じてきたものの、成約率が低く非効率な営業に陥っていたのが課題でした。そこで、インサイドセールスを導入したところ、温度感の高いリードを把握できるようになり、商談の質を高めることに成功したのです。
結果的に営業効率を高め、受注率のアップも実現しました。
メーリングリストの資産化を実現
成約や売上などに関する成功事例ではないものの、メーリングリストを資産化したケースがあります。
とある企業が数百件ものリードを獲得できているにも関わらず、ほとんど育成ができていないといった課題がありました。
そこで、インサイドセールスを導入して、ナーチャリングを実施しました。これに伴い、リードが抱えている問題や課題を把握しやすくなったのです。
今後の施策のヒントとなるペルソナ像のイメージも得られ、さまざまな場面に使える貴重なデータを得られるようになりました。
【関連記事】インサイドセールスで成果を出すためのコツは?業務課題別の解決策を解説
インサイドセールスにおけるおすすめコンサル企業5選
ここからは、インサイドセールスにおいて、おすすめのコンサル企業を5選ご紹介します。本当に効果の得られるコンサル企業に依頼したいと考えている方は、ぜひ以下の企業を候補として検討してみてください。
株式会社ファインドユニーク
インサイドセールスの導入で、まずおすすめしたいのが株式会社ファインドユニークです。当社は、中小規模の企業に特化したマーケティング会社であり、BtoB企業を中心に多くのノウハウがあります。
中小企業だからこそ効果の高いリード獲得方法や、よりターゲットに刺さるホワイトペーパーの制作方法などを熟知しているのが特徴です。
合わせて、デジタルマーケティングやSEOコンサルティングなど、「Web集客」にも精通しているため、さまざまな角度で企業の売上向上を支援します。
株式会社セレブリックス
出典:株式会社セレブリックス
株式会社セレブリックスは、セールスカンパニーとして、営業支援事業に特化している会社です。
時代に合わせた営業手法を駆使したコンサルティングや、最新の技術を用いた施策提案など、さまざまな方面でサポートしてもらえます。
「お客様の買わない理由をなくす」を同社の核として、課題解決に伴走している点が魅力です。また、営業支援事業とは別に、人材支援事業にも力を入れているため、人材不足の観点でも相談に応じてもらえます。
株式会社MOLTS
出典:株式会社MOLTS
株式会社MOLTSは、年間問い合わせ実績500件以上を誇るコンサル企業です。自社で実施している集客・リード獲得ノウハウを用いて、顧客にサービスを提供しています。
広告に頼らず、純粋な集客・営業を武器としている企業でもあり、同社独自のアンケートでは「クライアントの推奨率90%」といった結果もあります。
事業の成長にフォーカスしたサービスが特徴で、顧客ごとにフルカスタマイズでサービスを提供している点が特徴です。
ブリッジインターナショナル株式会社
ブリッジインターナショナル株式会社は、インサイドセールスやオペレーションアウトソーシング、マーケティングアウトソーシングなど、多岐にわたるサービスを提供しています。
インサイドセールスでは、徹底した教育を受けた専門社員が顧客の営業チームの一員となり、積極的にセールス活動を進めていくのが特徴です。
密に連携しながら、顧客の売上に貢献してくれるため、「細やかなサポートを受けたい」と希望している方にもおすすめできます。
株式会社H&K
出典:株式会社H&K
株式会社H&Kは、幅広い領域のコンサルティングを担っているのが特徴です。集客メインのWebコンサルティングや、経営にフォーカスした事業戦略コンサルティングなど事業は多岐に渡ります。
インサイドセールスに関するノウハウも豊富で、同社では積極的にインサイドセールスに関する情報発信を実施しています。
インサイドセールスのお役立ち情報として情報提供も豊富であるため、安心して依頼しやすいのが魅力です。
要点を押さえて効果的なインサイドセールスチームを立ち上げましょう
インサイドセールスの立ち上げには、綿密な計画と段階的なアプローチが欠かせません。自社の状況や目標を明確にし、それに合わせた戦略を立てることが重要です。また、フィールドセールスとの連携を意識し、組織全体としての営業力向上を目指すことが成功の鍵となるでしょう。
ツールの活用、他部署との連携、そして継続的な改善サイクルの実施。これらのポイントを押さえることで、効果的なインサイドセールスチームを構築し、営業成果の向上につなげることができます。立ち上げには時間と労力がかかりますが、長期的な視点で取り組むことで、必ず成果は表れるはずです。ぜひ、本記事で紹介したポイントを参考に、自社に最適なインサイドセールス体制の構築に取り組んでみてください。
【参考サイト】
インサイドセールスとは?立ち上げのポイントを解説|株式会社SALES ASSET