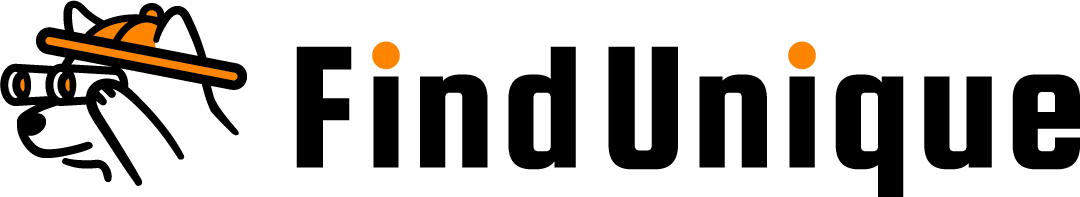製造業のブランディングとは?マーケティングとの違い・メリット・進め方を解説

製造業においても、価格や品質だけでは差別化が難しくなっている今、ブランディングの重要性が高まっています。「うちはBtoBだから関係ない」と思われがちですが、適切なブランディングを通し、信頼性や技術力を的確に伝えることができれば、顧客からの選ばれ方が大きく変わるのです。
今回は、製造業におけるブランディングの基本から、マーケティングとの違い、実施するメリットなどについて詳しく解説します。

本資料は、製造業がこれからの時代に必要とされる「Webマーケティングを取り入れた営業の仕組み」について解説しております。
どのようにWebマーケティングを自社の営業活動に取り入れていくかを具体的に解説しております。ぜひ参考にしてください。
製造業のブランディングとは
製造業におけるブランディングとは、企業や商品が持つブランドイメージを構築し、品質や価格だけではなく、見込み顧客から「この会社に任せたい」と感じてもらえるような印象づくりのことでもあります。
ブランディングが顧客・見込み顧客からのイメージにつながるため、「自社は顧客・見込み顧客にどのような印象を抱いてほしいのか」を明確にしなければなりません。
ブランディング次第で集客力も向上できるため、競争が激しいBtoB企業こそ必須の施策と言えます。
製造業のブランディングとマーケティングの違い
製造業のブランディングとマーケティングの違いとは、
マーケティングが自ら直接メッセージを発して相手に自分のイメージを伝えるのに対し、ブランディングは何らかの方法で相手に自分のイメージを持ってもらうことです。
極端にいえば、ブランディングは「顧客にイメージさせる」、マーケティングは「企業が伝える」点が違います。
| ブランディング | マーケティング |
|---|---|
| 顧客に「この製品がよさそう」「この企業から買いたい」と思ってもらう。 | 企業が「この製品がよい」「うちの企業から買ったほうがよい」と伝える。 |
マーケティングは「商品を売るための仕組みづくり」であり、集客・販売促進など、より具体性のある施策のことです。製品の強みや実績、技術力を適切なチャネルで発信し、顧客に理解してもらうことが目的とされています。
ブランディングは「企業や商品に対する印象をつくること」が目的で、顧客の信頼や共感を得る活動です。「○○といえばこの会社」と顧客に真っ先に思い浮かべてもらえる状態を目指すための取り組みです。認知度の話ではなく、顧客の頭の中にある「イメージ」を形成します。
同じような技術や価格帯の製品が複数存在する中で、ある会社の製品だけが「信頼できそう」「高精度な加工が得意そう」といったイメージがあると、それだけで購入率を引き上げることができます。結果的に価格競争に巻き込まれにくくなるのです。
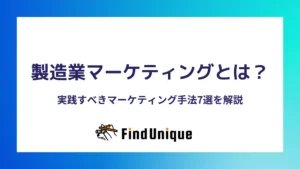
製造業のブランディングの種類と目的
製造業のブランディングは、大きく以下の4つに分けられます。
- インナーブランディング
- アウターブランディング
- 企業ブランディング
- 商品ブランディング
それぞれ、どのような特徴があり、何を目的として取り組むのか、詳しく見ていきましょう。
インナーブランディングとアウターブランディング
社内向けの「インナーブランディング」は、企業の理念やブランド価値を社員一人ひとりに浸透させる取り組みです。
「アウターブランディング」は、社外に向けた取り組みです。自社の商品やサービス、企業の価値を市場に伝える活動が主とされています。
それぞれの主な違いは以下の通りです。
| インナーブランディング | アウターブランディング |
|---|---|
| 社員の「ブランド理解」「共感」「行動の浸透」が目的。 | ブランドイメージの認知拡大、顧客の信頼獲得が目的 |
インナーブランディングは、社員の意識が統一され、モチベーションや帰属意識の向上が期待できます。全従業員が共通の認識・意識を持つため、結果的に一貫した対応・サービス提供につながるのが特徴です。
アウターブランディングは、広告やWeb、展示会などを通じて認知度を高め、顧客の信頼やブランドイメージを形成します。
企業ブランディングと商品ブランディング
「企業ブランディング」は、企業の理念や沿革、社会的責任(CSR)といった要素を通じて、「この会社は信頼できる」「共感できる」と感じてもらうことを目的としています。
「商品ブランディング」は、商品の機能や性能だけでなく、開発ストーリーや使用者の声、情緒的価値なども含めて伝える手法です。
| 企業ブランディング | 商品ブランディング |
|---|---|
| 企業への信頼感や好感、共感などを獲得していき、長期にわたって価値を高めていく。 | 商品そのものの魅力や差別化ポイントを伝えていき、購買を促進する。 |
企業ブランディングには、企業と顧客・社会との長期的な信頼関係を築けるというメリットがあります。採用活動でも企業の魅力が伝わりやすくなり、人材獲得においても有利になることが多いです。
企業ブランディングの具体的な施策としては、企業の理念を表すキャッチコピーをロゴに組み込むことや、ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を社内外に発信する取り組みが挙げられます。
商品ブランディングは、顧客が他社ではなく自社商品を選ぶ理由を明確にし、競合との差別化を目指します。特定のターゲットに対して、なんらかの印象を感じられる存在になることで、価格競争に巻き込まれにくくなる効果も期待できます。
具体的な取り組みには、商品名やパッケージデザインに一貫した世界観をもたせたり、商品コンセプトを伝える広告・LPの作成したりすることなどが挙げられます。
製造業がブランディングをするメリット
製造業がブランディングを始めるにあたり、そもそもどのようなメリットがあるのかは気になるところではないでしょうか。
期待できるメリットとしては、主に以下が挙げられます。
- 価格競争から脱却できる
- 自社製品や提供サービスのコンセプト明確化
- 採用活動で有利になる
- 取引先や顧客からの信頼度が上がる
- 社員のモチベーション・誇りが高まる
各メリットについて、以下から詳しく解説していきます。
価格競争から脱却できる
製造業がブランディングを実施するにあたって、まず挙げられるのが価格競争から脱却できることです。製造業が抱える課題の一つに、価格競争があります。
製造業界では、似たような製品が並ぶことが多く、顧客側としては「より安いほう」と比較されることは避けられません。
しかし、ブランディングで「高精度な加工なら○○社」「納期対応に強い△△社」といった選ばれる理由を確立できれば、価格以外の価値で顧客を惹きつけることが可能です。
たとえば、金属加工会社なら、「航空機レベルの品質管理体制」をブランドの軸とすることで、価格面以外で選ばれる理由が生まれます。製品力だけでなく、その裏にある技術面の背景や実績、信頼性を明確に発信することで、指名される企業へと脱却しやすくなるでしょう。
自社製品や提供サービスのコンセプト明確化
製造業は、ブランディングを実施することが、自社の製品・サービスのコンセプトの明確化につながります。ブランディングの過程で、製品やサービスが「なぜ価値があるのか」「他社と何が違うのか」を言語化するからです。
製品・サービスの魅力を言語化し、社内で共有されれば、営業担当も「うちの強みは高品質」という曖昧な説明から、「表面粗さRa0.1以下の加工が可能」「発注後2~3日で発送の即納体制」など、具体的で一貫性のある訴求ができるようになります。
コンセプトが明確になるだけでなく、社員一人ひとりが自社の強みを明確に認識できるため、提案の質や商談の成約率も向上します。結果的に、ブランディングが企業の利益に影響すると言っても過言ではありません。
取引先や顧客からの信頼度が上がる
製造業がブランディングを実施するうえで、メリットとなるのが取引先や顧客から信頼を得やすいことです。
BtoBの商談では、仕様や価格だけでなく「この会社は信頼できるか」が重視されます。ホームページや会社案内が古く、情報も統一されていない状況では、いくら技術力があっても相手に不安を与えます。
ブランディングでは、以下のような点を統一することが重要です。
- メッセージ
- デザイン
- 発信媒体
取引先に「信頼できる会社だ」という印象を与えるためにも、発信内容は一貫していなければなりません。
ホームページやSNS、チラシ、パンフレットなどの発信内容が不統一になっていないか、確認しておくことが重要でしょう。
社員の視点・行動がブランドに沿って変化する
製造業におけるブランディングは、社外へのイメージ向上だけでなく、社内の意識や行動にも変化をもたらす場合があります。ブランドの方向性や価値が社内で共有されることで、社員一人ひとりが「自社らしさ」を意識した判断や行動をとるようになるからです。
たとえば、「品質に妥協しない」というブランドメッセージが根付いていれば、現場でも細部へのこだわりや、ミスを防ぐための自主的な工夫が自然と行われます。また、「短納期で応える姿勢」を掲げていれば、納期厳守を前提とした工程管理や効率化のための視点などが現場で生まれやすくなるでしょう。
つまり、製造業におけるブランディングは、現場の行動指針になり、強みの維持や組織力の底上げにもつながっていくといえます。
採用活動で有利になる
若手人材の確保に苦戦している製造業にとって、ブランディングは必要な取り組みといえます。製造業は、他業種と比べて企業の魅力が伝わりにくいため、ブランディングで自社の技術や社会的意義、ビジョンを明確に外部に発信する必要があるのです。発信した内容が応募者の興味を引き、結果的に志望動機につながることも期待できます。
また、自社の技術力の高さや社会的な役割、業界No.1の実績(シェア)といった強みを明確に発信することも重要です。「評価されている会社だ」「この会社は倒産しなさそう」といった安心感につながるでしょう。
さらに、社員が参加する社内ワークショップの様子や、現場で活躍する若手社員の成長事例などを紹介することもおすすめです。入社した後の姿がイメージしやすくなり、応募者に「ここで働きたい」と思ってもらえるきっかけになります。
BtoBとBtoCのブランディングの違い
ブランディングと聞いて、華やかな広告やパッケージデザインを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。しかし、BtoBのブランディングは、BtoCとは異なり、「見せるもの」が異なります。具体的に、どのような違いがあるのか、それぞれ分けて解説します。
BtoBの場合
製造業は、顧客が法人であることが多いため、ブランディングでは「信頼できるパートナーか否か」が分かるような施策が重要です。
たとえば、製品の性能だけでなく、「納期を守れるか」「不具合発生時の対応力」「継続的な改善提案があるか」といった点も視野に入れる必要があります。技術力や品質体制、ISO認証、検査設備などQCDの取り組みをPRすることが重要です。
実際に、製造業界では、多くの企業が以下のようなコンテンツを公開している傾向にあります。
- 実績、事例の紹介
- 品質管理体制、取得している規格の掲載
- デリバリー体制、コストダウン場の様子
品質を訴求する際には、ただ主張するだけでなく、実績や導入事例、品質管理体制、ISO取得の有無など、客観的なデータをアピールすることが重要です。それぞれの情報は、企業としての信頼性や製品の安定性を裏付ける材料となり、取引先や求職者の安心感につながります。
その上で、自社がどの領域に強みを持っているかを明確にする必要があります。たとえば、コスト競争力に優れているなら、量産体制や原価低減の工夫を伝えるべきであり、納期対応に自信があるなら、スピーディな工程管理や短納期実績を前面に出すべきです。
上記の通り、強みに応じて訴求すべき内容は変わるため、自社のブランディング方針とQCDのどこに注力しているかを照らし合わせながら、情報発信を行うことが求められるでしょう。
BtoCの場合
BtoC向け製造業においては、製品の機能や品質だけでなく「印象」や「共感」も重視されることが大きな特徴です。実際、家電やアパレル、化粧品、食品、自動車、玩具、文具、家具などを製造・販売する企業では、顧客が製品に触れる前からブランドの印象が購買行動に大きく影響します。
消費者にとって、「おしゃれ」「安心感がある」「時代に合っている」といったイメージは、製品スペックとは別に重要な判断基準です。
SNSでの話題づくりや、印象的なパッケージ・デザイン、コンセプトに沿ったキャッチコピーなどで、「見た目」や「雰囲気」などの価値を訴求するケースが主流となっています。
そのため、BtoC向け製造業においては、「どんなに高品質か」よりも「どう感じられるか」「どんな世界観に共感されるか」といった印象の一貫性が、ブランド構築における重要なポイントとなるのです。
製造業のブランディングの大まかな進め方
製造業のブランディングは、適切な手順を踏んで進めていかないと、期待していた効果を得られません。
製造業として、ブランディングを成功させるためにも、以下のステップで施策を進めていきましょう。
自社の棚卸しを行う
現状分析で、自社の立ち位置を把握できたら、自社が持つ価値を再確認するために、棚卸しをしていきます。
棚卸しを行う際には、以下の点を明確にしましょう。
- 製品力・技術力
- 品質
- 納期対応
- 過去の実績
他社と比較した際に、優位性のある要素を棚卸しをしていくようなイメージです。
なお、自社の棚卸しは営業部門や製造現場の声も拾い上げることが重要です。現場視点だからこそ見えてくる独自の強みや、顧客がまだ気づいていない潜在的な魅力を発見できる可能性があります。
さまざまな部門と連携して、情報共有をしながら棚卸しを進めていきましょう。
現状分析を実施する
ブランディングの第一歩は、「自社の立ち位置を客観的に把握すること」です。顧客がどのように自社を認識しているか、競合との差異は何か、自社の強みや弱みはどこかなど、ヒアリングや定量的なデータにもとづいて洗い出していきます。
業界全体の動向や競合の状況、市場のニーズも含めて分析することで、ずれのないブランド戦略が立てやすくなるのです。なお、3C分析やSTPなどのフレームワークを活用するのも有効です。
| 3C分析 | 市場環境を以下の「3つのC」で整理するフレームワーク。 ・Customer(顧客):市場・顧客ニーズ・Competitor(競合):競合企業・Company(自社) :自社の状況 |
|---|---|
| STP | ターゲット設定とポジショニングを明確にするためのフレームワーク。 ・Segmentation(セグメンテーション):市場の細分化・Targeting(ターゲティング):狙う市場の選定・Positioning(ポジショニング):差別化ポイントの明確化 |
上記2つは、ブランディングでよく使われているフレームワークです。現状を分析する際に活用してみてください。
ブランドアイデンティティを構築する
現状分析と棚卸しを踏まえて、企業の核となるブランドアイデンティティを明確にしていきます。企業理念やビジョン、タグライン、ビジュアルデザインなどに言語化・可視化することで、一貫性のあるブランドアイデンティティを構築していくことが可能です。
事業の背景や創業者の想いといった「感情に訴えかける要素」も取り入れることで、記憶に残るブランドになります。ただロゴやスローガンを作るのではなく、「どんな価値観で行動するか」「どう振る舞うべきか」といった行動指針まで落とし込むことが重要です。
自社の情報を発信・浸透させていく
ブランドアイデンティティが明確になったら、社内外へ伝えるフェーズに移ります。WebサイトやSNS、展示会、営業資料などを活用し、ブランドメッセージを発信していきましょう。
企業がブランドメッセージを発信する場合、以下のような方法があります。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| Webサイト | トップページにキャッチコピーを取り入れる・「私たちについて」のページを設ける |
| SNS・ブログ | 開発秘話としてリアルな姿を発信する・ブランドイメージに合わせた文体を意識する |
| 営業資料・パンフレット | 提案書の冒頭やスライドタイトルに取り入れる・ブランドの価値観と製品の特徴をセットで公開する構成にする |
| 展示会・セミナー | ブースのビジュアルや配布資料のデザインに落とし込む・スタッフの服装・対応でブランドらしさを取り入れる |
なお、ブランドの周知は、社外だけでは不十分です。社員それぞれもブランドの内容を正しく理解して行動に起こせるよう、社内研修を実施したり、行動指針を浸透させたりする必要があります。
いずれも、一度の広告やキャンペーンで終わらせず、継続的な情報発信を行って、ブランドの定着・強化を図っていきましょう。
製造業のブランディングの具体的な進め方
製造業がブランディングを成功させるためにも、正しいステップを踏んでいきながら進めていく必要があります。ブランディングにおける全体のイメージとしては以下の通りです。
- 自社の強みや価値を言語化・定義する
- 自社の強みのコンセプト・キャッチコピーを決定する
- ブランディングを社内周知する
- さまざまなメディア・媒体でブランディングを打ち出す
- ブランディングの通りの行動を徹底する
各ステップについて、以下から詳しく解説していきます。
自社の強みや価値を言語化・定義する
製造業がブランディングを始めるのであれば、まずは自社の強みや価値について明確にする必要があります。自社の強みや選ばれている理由を明確にすることが、ブランディングの起点となるからです。
顧客の声や口コミ、営業現場での評価などから「なぜ自社が選ばれているのか」を分析し、技術力、対応力、スピード感、品質管理力といった要素を棚卸しをしていきましょう。
ポイントは、自社が思う「強み」ではなく、顧客が実際に価値を感じているポイントにフォーカスすることです。
現場担当者へのヒアリングや過去の提案資料の振り返りなどを通じて、客観的な視点からの情報を集めていきましょう。
自社の価値と判断できるポイントを言語化・定義することで、ターゲットの視点に置き換えたときに、「誰に」「どう役立つか」を発信へとつなげやすくなります。
自社の強みのキャッチコピーを決定する
自社の強みについて言語化・定義したら、キャッチコピーとして価値を表現できるようにしましょう。製品やサービスの差別化が難しいため、「印象に残りやすい言葉」を用いてアピールする必要があるのです。
キャッチコピーをつくる際は、まず「誰に対して何を訴求するのか(ターゲット×価値)」を意識します。自社の強みを短く、覚えやすく、印象に残る表現に落とし込むことが大切です。
主な例としては、以下が挙げられます。
- 1μの誤差も許さない品質管理
- 試作から量産まで、1週間で対応可能
- 最短3日、現場に届く即納体制
- 「できない」を、「できる」に変える現場力
具体的な表現や数字を用いたキャッチコピーは説得力が増します。
決定したキャッチコピーは、Webサイトのファーストビューやパンフレットの表紙、営業資料の冒頭など、あらゆる媒体で活用するため、丁寧に設計することが重要です。
ブランディングを社内周知する
ブランディングは、単純に「戦略設計して終わり」ではありません。社員がきちんと理解・共感していないと、実際の業務や現場での対応に、これまでと変化がない…といった事態に陥ってしまうからです。
まずは、経営層からブランドの背景や目的を社員へ丁寧に伝え、共通認識として浸透させていきましょう。単なるスローガンではなく、「どんな価値を社会に提供し、どんな姿勢で仕事をするのか」という行動指針として共有することが重要です。
また、営業・製造・開発・採用など各部門ごとに、ブランドに即した業務プロセスや顧客対応ができるよう実践を促す仕組みをつくりましょう。研修やガイドラインの整備、社内表彰制度、評価制度などにブランド要素を組み込むことで、日常業務に落とし込みやすくなります。
すべての社員がブランドイメージにもとづいた行動を徹底できるようにならないと、「スピード対応」を掲げているのに、問い合わせの返信が遅ければ信頼は一瞬で崩れてしまいます。納期の遵守、クレーム対応、製品の品質など、あらゆる顧客接点で「ブランド通りのふるまい」ができているかを意識してみましょう。
現場とのズレが生じた場合には、すぐに設計したブランドについて点検し、修正する仕組みの整備も必要です。常に「それはうちのブランドらしいか?」と問いかける文化が育てば、ブランディングは定着していくでしょう。
さまざまなメディア・媒体でブランディングを打ち出す
ブランディングについて社内周知が完了したら、社外へ打ち出していきます。
構築したブランドを社外に発信する際は、「媒体ごとにメッセージを一貫させる」ことを意識してください。Webサイトやパンフレット、会社案内であれば、冒頭部分でキャッチコピーを取り入れたり、デザインなどのビジュアルでブランドイメージを伝えたりすることが一般的です。
事例紹介や技術ブログなどで、自社の技術力や対応力を具体的に伝えることで、より理解を深めてもらいやすくなるでしょう。
SEO対策やSNS、メルマガなどのマーケティング施策も重要です。ユーザーとの接点を増やせれば、自社を何度も目にしてもらえるため、記憶してもらいやすくなるでしょう。
なお、展示会や営業現場でもブランディングを意識しなければなりません。製造業の場合、実際の製品や担当者のふるまいがブランディングにつながります。
媒体やシーンごとにイメージがぶれないよう、ブランドの世界観を統一することが重要です。
製造業のブランディングならファインドユニークへ
本記事では、製造業におけるブランディングの種類やマーケティングとの違い、進め方などについて解説しました。
製造業におけるブランディングは、ロゴやスローガンをつくれば良いというものではありません。自社の価値を言語化し、ターゲットに伝わる形で打ち出し、社内外に一貫して浸透させていく取り組みが必要です。
とはいえ、そもそもどのようなブランドで打ち出すべきか悩むケースや、自社の価値や顧客からのイメージが分からないといった事例は少なくありません。
ファインドユニークでは、そんな製造業界の企業に向けて、業界に特化したブランド設計やコンセプト開発を実施しています。設計したブランドをWebサイトやパンフレットへ展開することも可能です。
「強みをどう見せるべきか分からない」「技術はあるのに選ばれない」といった悩みを持つ企業の方は、ぜひ一度ファインドユニークにご相談ください。

本資料は、製造業がこれからの時代に必要とされる「Webマーケティングを取り入れた営業の仕組み」について解説しております。
どのようにWebマーケティングを自社の営業活動に取り入れていくかを具体的に解説しております。ぜひ参考にしてください。