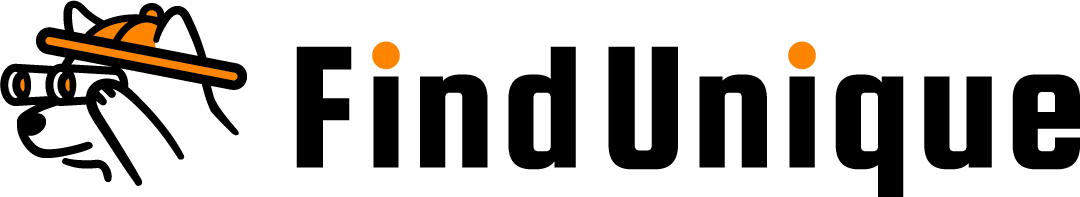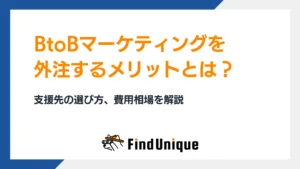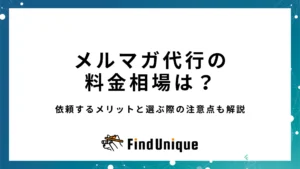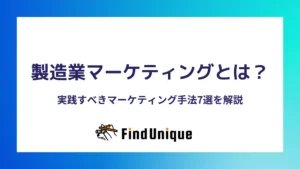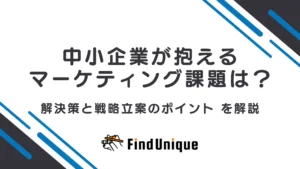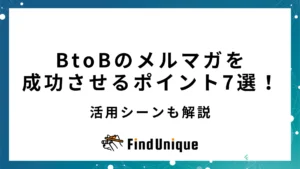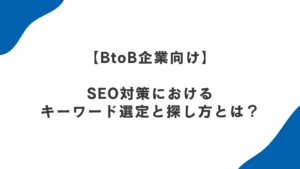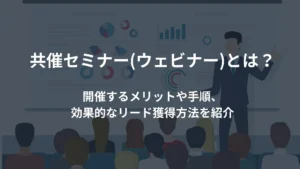MA運用に必要なスキルとは?おすすめのMAツールも解説!

MA運用を行うことが大切な時代です。MA運用はとくにどんな業務で可能なのか、またMA運用に求められるスキルはどんなスキルなのかが気になる場合も多いでしょう。
受注率アップのための運用ポイントや注意点を知りたい場合も多いため、MA運用で困らないためのポイントや注意点を詳しく解説します。
MA(マーケティングオートメーション)ツールとは
MAとは何かからまず見ていきます。MAとは「マーケティングオートメーション」の略です。マーケティングに関する業務を自動化・効率化するための仕組みやツールのことを言います。
MA(マーケティングオートメーション)には、そのためのさまざまな仕組みやツールがあり、上手に運用することが大事です。
MAでは、これまで人が行っていたマーケティングを自動化し、あらゆるデータを統合し、マーケティングを効率化していくことができます。
MAツールの導入・運用することで得られるメリット6つ
MAツールを導入する・運用することで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここからは、企業担当者が知っておくべき、さまざまなメリットを解説します。
業務効率化を実現できる
MAツールを導入・運用することで、現場の業務効率化を図ることが可能です。なぜなら、日常的に繰り返し発生するマーケティング業務を自動化し、担当者の作業負担を軽減できるからです。
例えば、メール配信のスケジュール設定やリードスコアリング、セグメント別のターゲティングといった作業をシステムが自動で実行できます。
また、データの収集や分析も自動化されるため、スピーディーに貴重な情報を収集したり、整理したりできるのが魅力です。
リードの育成や質の向上を期待できる
MAツールを導入・運用することは、リードの育成やリードの質を向上させることにつながります。
MAツールは、リード情報を一元管理でき、個々の関心・行動に応じた適切なアプローチを、自動で実施できるのが特徴です。実際、特定の商品に興味を示しているリードに関連する資料を送るなど、パーソナライズして業務を進められます。
また、MAツールの多くはリードのスコアリング機能を搭載していることがほとんどです。行動データや属性データをもとに、質の高いリードを識別しやすくなるため、結果的にコンバージョン率の向上も期待できます。
関連記事:リードナーチャリングとは?BtoBマーケティングにおける役割を解説
顧客とのコミュニケーションを最適化できる
顧客とのコミュニケーションを最適化できる点は、MAツールならではのメリットです。
MAツールは顧客データを一元管理するため、その中で記録されている行動履歴や興味関心などのデータをもとに必要なコミュニケーションを交わすことができます。
特定のページを訪問した顧客には、その商品やサービスに関連するフォローアップメールを自動送信したり、資料ダウンロード後に適切な次のアクションを促すリマインダーを送ったりできるのです。
双方の関係性を深めるためのコミュニケーションを実現できるのは、MAツールの大きな強みと言えます。
データドリブンなマーケティングができる
MAツールを導入・運用することで、データドリブンなマーケティングが可能です。
例えば、メール開封率、クリック率、サイト訪問履歴、購買履歴などのデータは、リアルタイムで取得することができます。取得したデータをもとに顧客のニーズや行動を予測し、効果的なキャンペーンを自動化できるのです。
また、データを分析し、どの施策が効果的であったかを定量的に評価できるため、PDCAサイクルを迅速に回せる点も魅力でしょう。
営業との連携を強化できる
MAツールの導入・運用は、営業との連携を強化することにつながります。なぜなら、MAツールを活用することで、マーケティングと営業の間で情報をリアルタイムに共有できるためです。
実際、リードの行動履歴やスコアリング情報を営業チームに速やかに提供できれば、営業担当がアプローチすべき優先順位の高いリードも効率的に共有できるでしょう。
また、MAツールを通じて、リードがどのコンテンツに関心を持っているかを把握することも可能です。そのため、営業はリードのニーズに沿った提案をしやすくなり、結果的に制約率の向上が期待できます。
関連記事:営業DXとは?営業課題をデジタルの力で解決するメリット・方法・ポイントを解説
チーム内での情報共有がしやすくなる
MAツールの導入・運用によって、チーム内での情報共有がしやすくなる理由は、データの管理方法にあります。
MAツールの特徴として「データを一元管理できる」が挙げられます。MAツールの中にデータを集約できるため、各々のメンバーがツールにアクセスすれば、いつでもデータを確認できるのです。
24時間、いつでもリアルタイムでデータにアクセスできるため、メンバーそれぞれが都合の良いタイミングで必要な情報を入手できます。そのため、情報共有のスタイルとしても、MAツールは優秀であると言えるのです。
MAツールの導入・運用の必要性
最近、MAツールの導入・運用の必要性が言われるようになったのかですが、次のようないくつかの要因があります。
顧客の購買プロセスの変化
コロナをきっかけに、顧客の購買プロセスが急激に変化してきたことも大きな要因です。最近では、多くの人が何かを買う場合に自分で情報を検索して調べてから購買します。
そのため、いかにそれぞれの企業などに合わせた情報提供が必要な時代かを考える必要があります。
ニーズの多様化
また、個々の顧客のニーズも多様化し、それに応える必要があります。抱えている課題や自身が気づいていない課題などがあり、どんなニーズを持っているのかを詳しく分析することが大切です。MAを運用して効率的に、多様なニーズを分析する必要が生まれています。
関連記事:BtoBマーケティングの施策17選!3つの目的別に解説
MAツール選びで確認すべき6つのポイント
MAツールを選ぶにあたって、確認すべきポイントがあります。初めて導入する場合は、以下の6点をおさえたうえで、ツールを選びましょう。
コストが予算内であるか
MAツールを選ぶにあたり、まずおさえたいポイントが「コスト」です。一口にMAツールと言っても、ツールによって費用差があります。
月額の利用料のほか、初期費用やオプションなどの費用もきちんと確認しておかないと、予算オーバーに陥ってしまう恐れがあるため注意が必要です。
また、MAツールは基本的に長期にわたって活用する点を踏まえたうえで、無理なく負担できる費用感のツールを選びましょう。
知識がなくても使いやすくシンプルな操作性か
MAツールを選ぶ際には、シンプルな操作性のタイプを選ぶことが重要です。管理画面が煩雑で使いにくいツールや、機能が多すぎて使いこなすのが難しいツールは、次第に使用頻度が下がる恐れがあります。
せっかくコストをかけて導入していても、きちんと活用できていなければ、損することになってしまいます。
とくに、システムやツールの利用に慣れていないメンバーも使用する場合は、抵抗なく操作しやすいツールを選ぶことが重要です。
他システムとの連携がしやすいか
MAツールを選ぶ際には、他のシステムと連携しやすいか否かをきちんと確認しておきましょう。
MAツールは、単独で利用することもありますが、他のシステムと連携したほうが、相乗効果を得られるため理想的です。たとえば、Web解析ツールやチャットツール、iPaaSツールなどはMAツールと相性が良い傾向にあります。
ただ、MAツールによっては、対応している他のシステムが少なかったり、連携までの流れが複雑である場合もあるため、「連携のしやすさ」はきちんと確認してください。
サポート体制が充実しているか
MAツールを選ぶにあたって、サポート体制は必ずチェックすべきポイントの一つです。
いざ導入してから「設定がうまくいかない」「使いたい機能が見つからない」など、さまざまなトラブルに陥ることがあります。サポート体制が充実していれば、各トラブルについて速やかに相談ができるため、解決もスピーディーです。
とくに、専任のカスタマーサポートがあるMAツールや、サポート担当者とのチャット機能が搭載されているツールは安心です。日常的に問合せがしやすいツールを選びましょう。
導入事例が豊富か
MAツール選びで迷ったときには、導入事例をチェックすることをおすすめします。導入事例が豊富であれば、多くの企業のニーズに応えられている証明です。品質や機能性なども一定の水準であると判断できるでしょう。
また、導入事例の中に、業界や企業規模が自社と似ているものがあるかをチェックすることも重要です。運用方法をイメージしやすくなり、導入してからの「想定していたように使いこなせなかった」といったトラブルを回避しやすくなります。
求める機能が備わっているか
MAツールを選ぶ際には、求める機能が備わっているかを確認しましょう。例えば、メール配信やリードスコアリング、行動分析、CRMとの連携など、自社が必要とする機能が足りていないと、活用しにくかったり、成果を得るチャンスを逃したりする恐れがあります。
とはいえ、多機能であるほど良いわけではなく、実際に活用できる機能が充実しているかがポイントです。まず「どんな機能を求めているのか」「どのような課題をMAツールで解決したいのか」などを明確にしてみましょう。
関連記事:中小企業がやるべきマーケティング施策とは?取り組む上での課題と解決策を解説
MAツール選びで迷ったら「HubSpot」がおすすめ
MAツールは、現在数多く展開されていることもあり、「結局どれが自社にマッチするのかが分からない」と悩む方が少なくありません。そんな方におすすめなのが、「HubSpot」です。
シンプルな操作感でありながら、機能が豊富であり、初めてでも使いこなしやすい点が魅力です。
スタートアップやスモールビジネス向けのスイートも提供されていて、必要最低限のコストでニーズに合った機能を活用できます。
また、連携可能なツール・システムは1700種類にも及ぶため、普段使っているツール・システムをそのままHubSpotと連携して活用できる可能性も高いでしょう。
使いやすさ、コスト、利便性などの観点から見ても、とくにおすすめできるMAツールと言えます。
MA運用の業務内容とは?どんな業務での運用が可能?
MA運用は実際にどんな業務で活用できるのかについても見ていきます。次のさまざまな業務内容で運用可能ですので、活用してみるのがおすすめです。
見込み客・潜在顧客の収集・分析
MAを運用した場合、ブログやサイトへの訪問者や、BtoBの場合には名刺交換や展示会などのデータを集めて、見込み客・潜在顧客のデータを広く収集できるようになります。
そして、獲得したリード情報をMAに格納することで、見込み客・潜在顧客のデータを収集するだけでなく、顧客のWeb上での行動を分析できることから、購買に結びつけるために育成する(ナーチャリング)も行えます。
顧客育成のためのナーチャリング
MAが一番得意としているのが、顧客育成のためのナーチャリングです。
BtoBにおいては、見込み客(リード)を獲得しても、すぐに購買→受注に移ることは珍しいです。そのため、実際購買してもらうように育成するナーチャリングが必要です。
そのため、ペルソナ設計や、見込み客の購買行動を示すカスタマージャーニーマップを作ることで、見込み客の購買行動の詳細や体験を理解できるように可視化します。
顧客のプロセスごとに、事業の課題を抽出して、ナーチャリングの設計を行い、具体的な施策をMAツールを活用して実装することができます。
この、マーケティングの全体設計、ナーチャリング施策の検討、MAによる施策の実行、この一連の流れがMA運用で一番重要なポイントです。
メール配信
また、MAはメルマガも配信することができ、企業が顧客に伝えたい新規サービスや事例などを配信することができます。
見込み顧客がメルマガを開封したか、どのページを見ているのかなども分析することができます。
ただし、MAを導入しても、メールやコンテンツのネタ切れという課題は、多くのMA運用の担当者を悩ませます。コンテンツを充実させるためには担当者のスキルも大事ですが、コンテンツ制作の外注も視野に入れても良いでしょう。
見込み客・潜在顧客(リード)管理
見込み客・潜在顧客(リード)管理も行えます。ツールによっては、スコアリング機能を使って購買意欲の高い見込み客(ホットリード)の抽出を行うなど、顧客の購買意欲を含めた管理が可能です。
見込みの低い顧客を後回しにできるため、適切に営業チームと共有ができれば、効率的にコンバージョンを獲得できるようになるでしょう。
データ分析および改善
MAを運用することで、メールのクリック率やコンテンツのアクセス履歴、離脱率などの多くのデータを効率的に分析できます。
これらの多くのデータをもとに、PDCAですぐに改善を行い、新たな施策を行えるようになります。分析から改善までの業務が効率化でき、社内でも多くの部署で、データ分析がすぐに見れるようになり、さまざまな角度やジャンルでマネジメントの分析や改善がしやすくなります。
MA運用に求められる5つのスキル
MA運用のスキルがないために運用がうまくできない場合も多くありますので、運用のために必要なスキルについて次に解説します。
MAの戦略設計のスキル
MA運用においてペルソナの作成やカスタマージャーニーの設計など戦略設計のスキルも必要です。見込み客の獲得のリードジェネレーションから育成のナーチャリングまで行って、営業へと引き継ぐスキルも不可欠となります。
他部署との連携、調整、進行管理のスキル
MA運用を成功させるには、マーケティング担当部署だけでなく、営業や広告、カスタマーサービスなど他部署とのさまざまな連携が必要です。
基本的に、MAツールは特定の部署のみで活用するものではありません。各部署がMAツールの情報にアクセスし、ビジネスチャンスへと繋げられるように有効活用していきます。
そのため、MAツールを効果的に活用するためにも、進行管理、調整を行うスキルなども必要となります。
MAツールの操作スキル
MA担当者がツール操作のスキルを身に付けることも大切なことです。営業ツールのSFAや顧客管理ツールのCRMとの連携もして、マーケティングをより効率化できるように、他のさまざまなツールについても理解を深めることが大事です。
実際、「せっかくMAツールを導入したものの使いこなせなかった」といった声は少なくありません。正しく活用できれば、MAツールは「かけたコスト以上の利益」につなげることが可能です。
そのため、MAツールの操作スキルは必須であるといえます。
コンテンツの企画、制作スキル
WEBサイトのコンテンツの企画や制作は担当者が行う必要があります。
コンテンツのクオリティは、ユーザーからの反響に直結する部分であり、極端に言えば「売上に大きく関わる部分」です。
どのようなテーマを取り上げるのか、誰に向けて何を伝えるのか、等はとくに厳選しなければなりません。
魅力的なコンテンツの企画制作のスキルがあるかどうかも大事です。
データマネジメントや分析のスキル
MAを運用する際は、顧客情報だけでなく、メール開封率、属性データ、行動データなど膨大なデータを管理するスキルが必要です。
また、MAで収集したデータを組み合わせて、分析を行ったり、PDCAでMA施策の改善を図っていくスキルが必要となります。しかし最初から分析のスキルを持つことは難しいため、MAツール作成元より支援してもらったり、外部からサポートを受けたりする方法もおすすめです。
MA運用の始め方
MAの運用の始め方のポイントとしては、小さく始めて効果を上げることも大切です。最初から、MA運用の社内体制が整わないことも多くあります。
まずは、MA運用を行うために、見込み客情報をたくさん収集し、MAツールにリード情報を入れ込み、定期的なメルマガ配信からスタートしてみるのもいいでしょう。
MA運用でよくある失敗例
MAはさまざまな業務で活用でき、効率化できることを紹介しましたが、運用が上手くいかない次のような例も多くあります。
- MAについての知識やノウハウがないメンバーで運用した
- MA導入時から複雑なシナリオを求めて導入した
- MA運用の担当者がいない、運用体制が整っていない
- コンテンツの充実、魅力的なコンテンツが作成できていない
これらの失敗例は、MAを導入した企業でよく見る失敗例です。
各失敗例について、詳しく解説していきます。
MAについての知識やノウハウがないメンバーで運用した
MAツールは高度な分析や設計などが必要です。そのため、MAに関する知識やノウハウを一切持たないメンバーだけで運用してしまうと、十分に活用できない恐れがあります。
たとえば、適切なターゲティングができず、リードが成果につながらないケースはよくある失敗です。こうした失敗を回避するためには、導入前に研修を実施することをおすすめします。
MAの基本的な知識や運用スキルを身につけたうえで、実際に導入することで「結局活用しきれなかった」といったトラブルを回避できます。
MA導入時から複雑なシナリオを求めて導入した
MAツールにおけるよくある失敗として、導入時点で複雑なシナリオを求めてしまうことです。
最初から複雑なシナリオ設計を求めると、運用がうまくいかないことがあります。
実際、条件設定が複雑すぎたり、過剰にセグメント分けを実施したりすると、作業フローが煩雑になってしまうことがあるのです。また、システムエラーのリスクも高まるため、基本的にはまずシンプルなシナリオ設計からスタートしていく必要があります。
MA運用の担当者がいない、運用体制が整っていない
MAツールは、運用の担当者がいなかったり、そもそも運用体制が整っていなかったりすると、失敗するリスクが高いと言えます。
実際に起こりうる具体的な失敗としては、「施策の進捗が停滞してしまう」「リードが適切に管理されず営業と連携できない」などが挙げられます。
MAツールの運用を失敗させないためにも、きちんと運用チームを編成して、担当者の役割を明確にしておきましょう。
コンテンツの充実、魅力的なコンテンツが作成できていない
MAツールの運用では、コンテンツの質が低いとリードを育成することが難しくなる場合があります。
例えば、ユーザーにとって価値のない情報や、興味を引かない内容のメールを送ると、開封率やクリック率が低下します。コンテンツが浅かったり、魅力のない設計であったりすると、コストや労力に対して成果が見合いません。
そのため、MAツールの運用を成功させるためにも、ターゲットに合わせた魅力的なコンテンツを作成する必要があります。ペルソナの設定や過去の反応データの分析を行い、コンテンツ戦略を練ることから始めてみましょう。
関連記事:営業とマーケティングの連携方法とは?成果に結びつくポイントを解説
MAを受注率アップにつなげる4つのポイント
MAを運用して受注率アップにつなげる具体的なポイントについても4つ挙げますので、参考にしてください。
MA導入の目的を明確にする
MAを何のために導入するのか、成果として何を求めるのかを導入前に明確にしておくことが大切です。
自社のマーケティングの課題や強化したいポイント、効率化したい業務を明確にしておくことが重要です。
導入ツールの検討
また、MAツールにもさまざまなツールがありますので、自社の課題や強化ポイントのために必要な導入ツールをよく検討して導入することが大切です。
MA運用体制の構築
MAの運用体制ができていないため、上手く運用できないことが多くあります。
例えば、MAの運営責任者、メールマーケティング、効果測定、顧客管理など、業務ごとにMA担当者を配置しておくことも大切です。営業部門やカスタマーサービス部門など、社内の連携部署との役割分担もしっかりしておくことがおすすめです。
ペルソナ設計・カスタマージャーニーマップの作成
ペルソナ設計とカスタマージャーニーマップの作成が重要です。顧客のニーズ課題を検討フェーズ毎に明確にすることで、MAでどのようなコンテンツを配信すべきかを明確にすることができます。
また、カスタマージャーニーマップがあれば、閲覧ページやダウンロードした資料から、顧客の購買意欲や知りたい情報を予想して配信することができます。その結果、自社サービスの必要性喚起ができることで、商談化につなげることができます。
MA運用においてとくにチェックすべき効果指標
MA運用では、さまざまな効果指標が存在するため、「どこに注視すべきか」で迷う方が少なくありません。実際、会員登録に関するデータやユーザー属性、購入履歴など、多岐にわたります。とはいえ、全ての効果指標をこまめにチェックするのは難しいのが現状です。
ここからは、MA運用において、とくにチェックすべき効果指標をピックアップして解説します。
メルマガの開封率
メルマガの開封率とは、自社が配信したメールが、どの程度開封されたのかを示す効果指標のことです。
具体的な計算方法は以下の通りです。
【メルマガ開封率の計算方法】
メルマガの開封率=配信数÷開封数
開封率が高いほど「ユーザーの関心を引けている」と判断できます。一方、開封率が低ければ、メルマガのタイトルや配信タイミング、ターゲティングなどを見直す必要があるでしょう。
つまり、メルマガの開封率を測定することは、「件名に問題がないか」を見極めることにつながり、改善につなげるためにも必要です。
ちなみに、メルマガの開封率は一般的に20%前後であるといわれています。自社のメルマガの開封率と照らし合わせ、一般と比べてどの程度差があるのかをチェックしてみてください。
メルマガの開封者数
MA運用でチェックすべき指標の一つが「メルマガの開封者数」です。前項の開封率とは異なり、実際に開封したターゲットが何人であるのかを示す指標です。
とはいえ、単純に開封された数をチェックするだけでは、対応としては不十分でしょう。新規顧客向け・既存顧客向けそれぞれのメールで開封者数を比較したり、開封数が多かったタイトルを分析したりするなど、開封者数に基づいた調査が必要です。
ちなみに、メルマガの開封者数は、イベントやキャンペーンの内容を配信した際に「どの程度アプローチできたか」のヒントにもなります。開封率の情報も参考にしながら、自社の現状と課題、今後の解決策について考えていきましょう。
メルマガのクリック数(サイト誘導者数)
メルマガのクリック数とは、メルマガ内のリンクがどの程度クリックされたのかを示す指標です。つまり、メルマガを通じて、ターゲットをサイトに誘導できた人数を表します。
メルマガのクリック数が分かれば、各セグメントでの比較検証がしやすくなります。想定していたよりもサイトの誘導者数が少ない場合は、配信内容の調整やランディングページの最適化をふまえ、全体的な設計を見直す必要があるでしょう。
メルマガのクリック率(CTR)
メルマガのクリック率(CTR)とは、本文の中に挿入したリンクがクリックされた割合のことです。イベントページや製品ページなどのリンクを挿入した際に、どの程度の割合でクリックされているのかが分かります。
メルマガにおけるクリック率の計算方法は以下の2つが挙げられます。
【メルマガのクリック率】
・クリック率=開封数÷クリック数
・クリック率=配信数÷クリック数
ただ、クリック率を調べるうえで、とくに重要なのは「開封数÷クリック数」の計算方法です。そもそも、クリック率を計算する目的は、メルマガ本文を読んだユーザーのうち、どれくらいの割合がリンクをクリックしたのかを調べることです。
そのため、配信数を分母で計算してしまうと、メルマガを開封していないユーザーも計測対象として含まれてしまいます。
クリック率を計算する際には、開封数を分母にして計算することを忘れないようにしましょう。
ちなみに、メルマガのクリック率は、開封率や開封数とは異なり、「ターゲットが魅力的に感じたか否か」「きちんと関心を引けているか」などを分析できる指標です。
メルマガのクリック率は、一般的に5%前後であり、低い傾向にあります。そのため、リンクをクリックしたくなるような文言(CTA)を設置したり、本文・リンクのデザインを調整したりすることが重要です。
メルマガのコンバージョン率(CVR)
MA運用でチェックすべき効果指標として、メルマガのコンバージョン率が挙げられます。
メルマガを経由してサイトに訪問したユーザーの何割が購入・問い合わせなどのコンバージョンに至ったかを示す指標です。
本来のゴールであるコンバージョンの指標は、各効果指標の中でもとくに注視すべきポイントでしょう。
仮に、サイトに訪問したユーザーの人数に対し、コンバージョンが低い場合は、サイト側のUI・UXに問題があったり、フォームの分かりにくかったりする場合があります。コンバージョン率の結果を見ながら、適宜サイトを改善していくことが求められるでしょう。
メルマガのコンバージョン数
メルマガのコンバージョン数は、メルマガを通じて自社サイトにアクセスしたユーザーがコンバージョンまで至った数を示します。
一般的には、コンバージョン率に注目されることが多いですが、期間限定のキャンペーンや、特定のプロモーションなどを実施している場合は、コンバージョン数のチェックを重視することが多いです。
とくに、期間限定で施策を実施する場合は、目標とするコンバージョンを決定していることが多いため、必然的にコンバージョン数がチェックすべき指標となります。
Cookieを付与できている数
Cookieをどの程度付与できているか、といった点はMAの運用において確認が必要な指標です。
サイトに訪問したユーザーがCookieを受け入れていれば、その後の行動を追跡できるためです。ユーザーの行動をヒントにしながら、個別のマーケティング施策を実施できます。
つまり、Cookieの付与数が明確になれば、配信したメルマガがどれだけリターゲティングに貢献しているのかを把握することにつながるのです。
MA運用を成功させるための大切なステップ
MA導入から運用まで、MAが定着するまでのステップとして大切にしたいことですが、次のようなステップを踏むことが重要となるでしょう。
1.取引前の見込み客情報を収集する
MA運用を成功させるために、まず必要なのが「見込み客の情報を集めていくこと」です。取引前の見込み客について、きちんとデータを収集しておくことにより、以降で実施するリード育成やセグメント分けなどがスムーズに進められます。
仮に、営業や展示会などで見込み客と名刺交換している場合は、名刺に記載されている情報も集めていきましょう。
ほかにも、新規の見込み客の情報を収集する方法として挙げられるのが、資料請求やホワイトペーパーダウンロード、ウェビナーなどへの参加登録などで得ることです。
また、ダウンロード・登録の工程で使用するフォームは、欲しい情報が得られるように設問やアンケート内容を調整することも大切です。
2.複雑なシナリオの前に定期的なメール配信を計画する
MA運用では、はじめに複雑なシナリオを設定するのは好ましくありません。まずは、定期的なメール配信について計画を固め、今後の運用の基礎を作っていく必要があります。
定期的にメールを配信できるようになれば、見込み客に継続的に情報を提供できます。提供したい情報を発信しつつ、見込み客との接点にもなるため、「ブランド認知の向上」「信頼関係の構築」など、さまざまなメリットを得られるでしょう。
ターゲットに合わせて、配信タイミングや配信頻度を調整し、メルマガの内容も「価値があること」を重視して取り入れることが重要です。
3.Webページのサマリを配信コンテンツとして活用する
既に、自社のWebページでサマリやブログ記事があれば、配信コンテンツとして活用することをおすすめします。
既に、既存サマリ・記事があれば、ゼロから配信コンテンツの内容を考える必要がなく、効率的にメルマガ制作を進めることが可能です。さらに、メルマガ内に既存コンテンツへのリンクを設置すればアクセスを促しやすくなり、結果的に流入数を底上げできます。
また、既存サマリ・記事の要点をまとめたコンテンツを配信するだけではなく、新商品の紹介ページを作成した際に、そのページへアクセスを促すためのメルマガを作成することも効果的です。
工夫次第でさまざまな形での流入を実現できるため、「どこにアクセスが欲しいか」を視野に入れながら、メルマガの内容を設計していきましょう。
4.メルマガ配信結果からリード評価を行う
メルマガを配信して一定期間が経過したら、配信結果を調査してリードの評価を実施していきます。
開封率やクリック率、サイト訪問数、コンバージョン率などはリードにおける関心度の高さや購買意欲の強さを数値化するためのヒントになります。各指標を深く分析していくことで、アプローチすべきリードや施策の優先順位が明確になったり、課題の早期発見につながったりするため、必要なフローです。
なお、リード評価はMA運用を継続する限り、定期的に実施し付ける必要があります。評価するタイミングやルールをきちんと整備し、常にPDCAサイクルを回していけるようにしましょう。
5.リード評価に合わせて営業アプローチを行う
リード評価が明確になったら、営業アプローチを実施していきましょう。そのためにも、まずは、アプローチすべき見込み客の優先順位などのデータを営業チームに共有します。
情報共有の後は、営業担当者から見込み客へ直接コンタクトを取って、ヒアリング・提案を実施していくことが基本です。ただし、営業が直接コンタクトを取るのは、あくまでも「スコアの高いリード」に限定してください。
スコアの低いリードは、購買意欲や関心を高めるためのアプローチが必要な段階です。そのため、メルマガの定期配信で育成していく必要があります。リードの評価をきちんと行うことが、アプローチの最適化につながるため、慎重に分析していくことが重要です。
6.MA担当者の教育・スキルアップを進める
MAツールの運用には、MA担当者の教育も大切です。ツールの基本的な使い方から応用的な使い方までを実際に学んでスキルを上げる必要があります。実際、MA運用で使用するツールは、機能性が豊富なケースも多く、担当者自身が把握していない使い方があるケースも珍しくありません。
そのため、MAツールの機能を充分に使いこなせるようスキルアップしていくことも大切なことです。
教育・スキルアップの方法としては、ツールを提供する会社が開催しているセミナーに参加したり、社内でマーケティングやデータ分析に関する勉強会を実施したりすることが挙げられます。
ツールの提供会社によっては、専任のサポーターが担当としてつく場合もあるため、MA運用ツールを選ぶ際のヒントにしてみてください。
7.MAの効果測定と改善を繰り返す
MAツールの運用を始めたら、効果を定期的に測定することも大切です。その結果をもとに、PDCAで、MAの設定や使い方を改善していきます。
KPI(重要業績評価指標)は、最初に設定したビジネス目標やマーケティング目標に直結するものを選び、数値で分析していくといいでしょう。
A/Bテストなどを行い、メールマーケティングやランディングページなどの改善を図ることなども効果的な方法です。
MA運用時の注意点と解決策について
MA運用時の注意点と解決策についても最後に見ていきます。事前に運用の注意点や解決策も知っておくと失敗せずに済んでいいでしょう。
MA運用で課題を解決し成功させるための注意点
MAは、マーケティングを自動化し効率化して、マーケティング担当者の負担を軽減することができるツールです。しかし、実際には「メール配信ツールとして使っているだけ」といった場合もあるため注意が必要です。
運用が上手くできず、マーケティングの課題が解決できていないということにならないように注意してください。
MA運用を成功させるための解決策
MA運用を上手く行い、運用でつまずかないようにするためには、導入の事前準備をしておくことが解決策です。
MA運用で失敗しないために、MA導入についての知識やスキルで不安がある場合には、最初からMAツール作成元などのサポートを受けてみるのも解決策と言えます。運用のための社内体制も事前にしっかり作っておくことが大切です。
初心者にもおすすめのMAツール6選
MA運用を検討しているものの、社内で活用した経験がなかったり、ノウハウがなかったりするケースは多いものです。そこで、ここからは初心者でも使いやすいMAツールをご紹介します。
「わかりやすさ」「使いやすさ」にフォーカスして厳選していくため、ぜひツール選びの参考にしてみてください。
Hubspot
出典:Hubspot
Hubspotは、世界135か国以上の企業が導入しているMA運用ツールです。マーケティングやカスタマーサービス対応、営業など、各領域の情報を集約できるのが特徴です。
利便性も高く、同ツール内でキャンペーンの作成から公開まで進められます。また、公開後の測定もツール内で簡単に実施できるため、初めてでもクオリティの高い分析が可能です。
連携できるアプリやツールも豊富です。SlackやGmail、zapierなど、普段業務で利用しているツールと連携できるため、より便利に活用できるでしょう。
SATORI
出典:SATORI
SATORIは、初心者向けのMAツールとして人気を集めているのが特徴です。導入実績は1500社以上にも及び、大手メディア・グループも活用しています。
同ツールの最大のと特徴は「匿名の見込み客へのアプローチが可能」な点です。仮に名前が分からない見込み客であっても、接点を設けることができます。
また、問合せ前の段階にある匿名ユーザーの行動履歴や、興味関心の度合いなどを測ることも可能です。アプローチにおける最適なタイミングも提案してもらえるため、成約チャンスも高めやすいでしょう。
Account Engagement
Account Engagementは、BtoBに特化したMAツールです。視認性が高く、直感的に理解しやすい操作画面が魅力であり、初心者にもやさしいツールといえます。
また、各ファネルにおける認知度の状態を把握しやすいのも魅力です。AI技術を活用し、購入に至るまでのフローをスムーズに進めやすくしてくれます。
担当者の教育として活用できる「無料の学習コンテンツ」も充実している点は、同ツールならではでしょう。基本的な使い方やビジネスマーケティングの向上方法、リード生成・育成までのフローなどについて学べます。
Kairos3
出典:Kairos3
Kairos3は、親しみやすいデザイン性が特徴のMAツールです。ユーザーの行動を可視化したツールであり、購買意欲が高いユーザーや成約チャンスが高そうなユーザーを直感的に把握できます。
初めての方でも使いこなせるよう、サポーターが支援してくれます。フォーム作成の方法やタグの付け方などで悩んだときにも、すぐに相談・解決できるのが魅力です。
ちなみに、デモを提供しているため、実際に導入する前に使用感や得られるデータなどを確認できます。導入を迷ったときには、一度デモで試してみると良いでしょう。
Adobe Marketo Engage
Adobe Marketo Engageは、世界的に有名な企業である「Adobe」が提供しているMAツールです。
収益を最大化することを目指したツールであり、企業の売上に直結する機能が豊富です。高い精度でオーディエンスのターゲティングが実現できたり、企業の製品やブランドなどに合わせてAIをトレーニングしたりできます。
自動ナーチャリングやコンプライアンス対応、リート拡大など、魅力的な機能も豊富です。顧客だけではなく、見込み客に対しても一貫性のあるアプローチを実施できます。
b→dash
出典:b→dash
b→dashは、中小企業から大手企業、スタートアップなど、国内の導入実績が豊富なMAツールです。
MAツールでありながら、Web接客やBI、CDPなどの機能も保有していて、さまざまな活用方法があります。コード不要でデータも構築できるため、エンジニア不足の現場でも重宝します。
ユーザー一人ひとりの行動ログを管理したり、LINEと連携してセグメントに配信したりするなど、便利な機能も充実している点が魅力です。
まとめ
MA運用についてどんな業務で運用が可能なのかについて見てきました。見込み客・潜在顧客の獲得(リードジェネレーション)や育成のナーチャリングまで行え、メール配信、コンテンツ作成の自動化、効率化、見込み客・潜在顧客(リード)管理、魅力的なコンテンツのための維持や管理、データ分析及び改善の業務が行えるのが魅力です。
MA運用を成功させるためのポイントも知って、運用体制を整えてみることがおすすめです。注意点についても解説しましたので、運用のための準備もしっかり行い、MAで効率化を図ってみるといいでしょう。
ちなみに、ファインドユニークでは、中小企業に向けたマーケティングやコンサルティングサービスなどを提供しています。
MAツールの活用と合わせ、より戦略的なSEO対策を実施したいと考えている企業担当者の方や、MAツールとの相乗効果を見込んでマーケティングを実施したいと考えている方に向けたサービスです。
お見積りのみ、お問い合わせのみ、など無料で対応していますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。