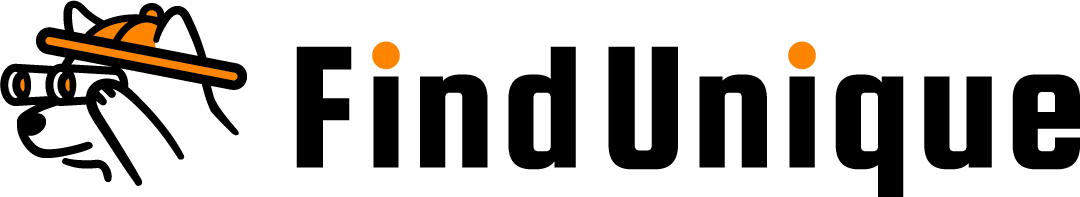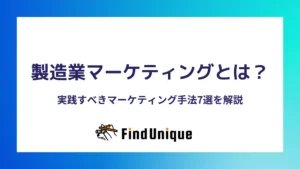製造業のリード獲得手法とは|おすすめ施策や成功のポイントを解説

製造業界において技術力や製品品質は重要であるものの、それだけでは新規顧客の獲得は難しいものです。BtoB取引が中心となる製造業では、受け身の営業スタイルから脱却し、戦略的にリードを獲得していく仕組みが必要といえます。
この記事では、製造業におけるリード獲得の課題や、実践すべきリード獲得の施策を解説していきます。従来のやり方に限界を感じる担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

本資料は、製造業がこれからの時代に必要とされる「Webマーケティングを取り入れた営業の仕組み」について解説しております。
どのようにWebマーケティングを自社の営業活動に取り入れていくかを具体的に解説しております。ぜひ参考にしてください。
製造業のリード獲得とは
製造業におけるリード獲得は、単にWebサイトへのアクセス数を増やすことではありません。
本質的には、次のような構造で成り立っています。
| リード獲得 = 集客力 × リード化コンテンツ |
ここでいう「集客力」とは、Webサイトにどれだけ見込み顧客を呼び込めるかという指標です。具体的には検索エンジンからの流入や広告、SNSなどを通じたサイトアクセス数が該当します。
一方「リード化コンテンツ」とは、サイト訪問者が自ら情報を入力したくなるような、見返りとなる資料類や情報資産を指します。製造業では特に次のようなコンテンツが効果的です。
- サービス資料(製品ラインアップ・導入事例など)
- ホワイトペーパー(業界課題や技術解説をまとめたPDF)
- 技術データ(スペック表、CADデータ、検査成績書など)
「集客力」と「リード化コンテンツ」のどちらか一方でも弱ければ、リード獲得は思うように進みません。
見込み顧客を集める導線設計と、興味を引く価値を提供することの両立が重要です。
BtoBの製造業では、購買までに長い検討期間を要するケースが多いものです。そのため、情報収集段階の見込み顧客に早期から接点を持っておくことが重要です。
なお、リードは獲得して終わりではありません。その後の「育成(ナーチャリング)」も必要です。顧客の興味関心を高めていき、「この会社の○○製品が欲しい」といった状態まで育成していく必要があります。
段階的に信頼関係を築いていくことで、長期的な関係を築くことにもつながるため、リード獲得がゴールにならないように意識しなければなりません。
リード獲得とリードの育成・教育(ナーチャリング)の違いとは
リード獲得とリードの育成・教育の主な違いは、下記の通りです。
| リード獲得 | リードの育成・教育 |
|---|---|
| 将来的に顧客になる可能性がある、見込み顧客(リード)の情報を獲得する活動 | 獲得したリードの購買意欲を高めるために育成する活動 |
リード獲得は「見込み顧客の情報を獲得する活動」、ナーチャリングは「そのリードを育てること」です。
主な施策としては、以下が挙げられます。
【リード獲得】
- ホワイトペーパーのダウンロード施策
- SEO記事+資料請求CTAの設置
- 展示会・ウェビナーでのリード収集
- メルマガ登録
- チャットボットによる見込み顧客ヒアリング
【リードの育成・教育】
- ステップメール
- 技術ブログ・コラムの定期配信
- 導入事例コンテンツの公開
- 営業チームとの連携
工作機械メーカーを例とすると、まず「精度の違いによる加工品質の比較資料」をホワイトペーパーとして提供し、ダウンロードしたユーザーに対して、メールで「加工精度で失敗しないためのチェックリスト」や「他社導入事例」を定期的に配信するのが育成・教育に該当します。
製造業の場合、商材単価が高くなればなるほど、初回の接点だけで購買につながることは難しいです。顧客の検討フェーズを読み取り、適切な情報を適切なタイミングで提供できるかが成約可否に関わります。
製造業のリード獲得における課題
製造業を営む企業の中には、優れた技術力・製品があっても、それを市場に伝えられていないケースは少なくありません。結果的にリード獲得のチャンスを逃している場面も多く見られます。
製造業のリード獲得における課題について詳しく解説していきます。
Webサイトが顧客の求めている情報を整理できていない
製造業のリード獲得における課題として、まず挙げられるのがWebサイトの設計ができていないことです。製造業のWebサイトを見てみると、製品の仕様や図面を並べただけで終わっているケースが少なくありません。
「導入後に生産性が◯%向上した」「異常停止が月に◯回減った」といった効果を数値で示すと、見込み顧客の関心を引きやすくなります。Webサイト上で自社の強みや導入によるメリットが伝わらないと、せっかく訪問したユーザーが離脱してしまうため、スペック重視で訴求してもリード獲得にはつながりません。
また、顧客が製品の検討段階にあるのか、課題を認識し始めた段階にあるのかに応じて、届ける情報も変える必要があります。検討初期には課題解決コンテンツ、中期には比較資料、後期には導入事例やFAQといった情報が求められるものの、それが整理されていないと、「どこに何があるか分からない」と離脱されてしまうのです。
なお、Webサイトにおいては、リード化コンテンツの導線についても注意点があります。お問い合わせフォームがフッターの一番下に小さく配置されていたり、資料請求ボタンが目立たなかったりと、リード化コンテンツへの導線が弱く、リードを取りこぼしてしまう構造では集客ができません。
せっかく良質なコンテンツを用意していても、ユーザーがたどり着けなければ意味がなく、「どう見せるか」「どこに配置するか」といった導線設計はリード獲得に直結します。
集客ができていない
多くの製造業では、SEO対策が十分に行われておらず、検索エンジン経由の流入がほとんどない状態に陥っています。
本来であれば、「◯◯の加工方法」や「業界別 導入事例」など、見込み顧客が検索しやすいキーワードを意識したコンテンツを設計することで、自然検索からの流入とリード獲得を狙うことが可能です。
しかし、現状は検索ニーズに合った情報が用意されていなかったり、そもそもGoogleに正しく評価されていないページも多く、せっかくのリード獲得の機会を逃している企業が少なくありません。
「集客ができていない」という課題の根本には、検索経由の見込み客との接点が不足しているといった問題があるのです。
マーケティングにかける予算が確保できない
製造業では「マーケティング=展示会」といった考えが根強く、限られた予算の多くがブース設営や出展費用に集中してしまい、Webを活用したリード獲得やブランディングへの投資が後回しにされやすい傾向にあります。
また、マーケティングを専門で担当する人材がいない、または育成されていないケースも多く、ヒト(人材)・モノ(コンテンツ)・カネ(予算)のいずれも不足しているのが現状です。
そのため、「そもそも何から手を付けていいかわからない」「予算があっても展示会で使い切ってしまう」といった事態にも陥りやすく、継続的に成果を出せるマーケティング体制が構築できない企業が少なくありません。
また、リード獲得の手段として、展示会などに依存していると、コロナ禍や景気後退の影響で展示会が中止になった際に、代替手段がありません。実際に、パンデミックや不況が原因でリード獲得が止まってしまった企業もあります。
Web広告やSEOコンテンツなどのオンラインチャネルを活用できれば、上記のような影響を受けにくく、リード獲得がストップすることも避けられます。
今後の世界情勢もどうなるのかは分からないため、オンラインのリード獲得手段を持っておくことは重要でしょう。
マーケティングのノウハウが不十分になっている
製造業の大きな課題ともいえるのが、マーケティングに精通する人材がいないことです。ノウハウが不十分な状態で営業や総務が兼務しているケースが少なくありません。
Webマーケティングやコンテンツ運用に関する知見がないと、Webサイトをリニューアルしたいときや集客のためにSEO対策を実施したいと検討しても、実現することが難しいといえます。
リード獲得を成功させるには、Webサイト・広告・メール・営業支援などを一貫して設計・改善していく知見が必要です。
それを担う人材や体制が整っていないことが、多くの企業にとっての根本的な課題です。
製造業におけるリード獲得の手順
製造業がリード獲得を成功させるためにも、正しい手順に沿って進めていくことが必要です。ここからは、製造業におけるリード獲得の正しい手順について解説します。
ターゲット・ペルソナを明確にする
製造業がリードを獲得するためにも、まず実施すべきなのがターゲットを明確にすることです。
たとえば、「関東圏に本社を置く、従業員50~300名の精密部品メーカー」「生産性向上や不良品削減に課題を感じている製造部の課長」など、業種・企業規模・地域・役職・課題といった切り口で分けて整理することがポイントです。
また、難削材加工のノウハウや一貫生産体制など、自社の強みが刺さる相手が誰なのかを洗い出し、ターゲットごとに訴求メッセージを整理しておきましょう。Webサイトや広告、展示会など、各媒体での一貫した情報発信が実現できるようになるため、よりターゲットからの反響を得やすいアプローチにつながります。
購買フローマップを作成する
ターゲットを明確化したら、購買フローマップを作成します。ターゲットが「情報収集→課題認識→比較検討→問い合わせ→受注」に至るまでの購買プロセスを可視化するのです。
たとえば「まず技術者が課題を認識→上長が予算承認→購買部門が最終判断」といった流れを想定するなら、各フェーズで顧客が求める情報と行動(Web検索など)を整理します。
具体的には、以下のようなイメージです。
| 購買フロー | 提供すべき情報(コンテンツ) |
|---|---|
| 技術者が課題を認識 | 仕様書、図面、スペック、比較資料等 |
| 購買部門が業者選定 | コスト、納期、サポート体制、規約関連等 |
| 上長が予算承認 | 効果、成果数値、コスト、導入成功事例 |
営業・マーケティング施策と顧客の行動がズレていないかを可視化できれば、ボトルネックの特定や施策改善にもつながります。
集客の施策を実施する
ターゲットや購買フローが整理できたら、次のステップは「見込み顧客をWebサイトへ呼び込む=集客」です。ここで注意したいのは、集客とリード獲得(情報取得)は別のフェーズであるということです。
まずは「どのようにサイトへ流入させるか」という視点で、チャネルごとに戦略を立てていく必要があります。
■集客の代表的な施策
| SEO施策 | 製品名や業界用語、技術キーワードで検索されることを想定し、オウンドメディア(技術ブログや事例記事等)でコンテンツを公開する。 |
|---|---|
| リスティング広告 | 「部品名+課題」「製造方法+比較」など、ニーズがある検索語句に対して、Google広告等で即効性のある流入を獲得する。 |
| ディスプレイ広告/SNS広告 | 業界特化のメディアやLinkedInなどにバナー広告を配信し、認知・流入を広げる。 |
| 展示会と連携したWeb告知 | 出展前にLPや特設ページを公開し、SNSや広告で事前集客を図る。出展後には来場者向けのアフターフォローページで接点を深める。 |
Web経由のリード獲得を実現するには、「どのようにして見込み客を呼び込むか=集客の導線」を戦略的に構築することが必要です。
そのうえで、リード化コンテンツ(ホワイトペーパー、技術資料、導入事例PDFなど)につなげ、情報取得(リード獲得)へとつなげる設計が効果的でしょう。
集客で得た見込み顧客をリード化(個人情報を獲得)する
展示会やWebサイトでユーザーとの接点を得ても、名刺交換やフォーム入力などを通じて個人情報を取得できなければ、リードとはなりません。リード化するには、ユーザーが自発的に情報を入力したくなるような価値を提供する必要があります。
製造業であれば、製品カタログのほか、ホワイトペーパーや技術データ、検査成績書、価格ガイド、導入事例など、専門性の高い情報コンテンツが有効です。特に、ユーザーが課題を認識し始めた段階では、比較・検討に役立つ資料や技術的なデータが求められます。専門性を打ち出せるホワイトペーパーや、技術力・スペックが分かる技術データ資料を適切なタイミングで提示できることが重要です。
しかし、ユーザーがその情報にたどり着き、自然な流れでフォームへ進めるように導線を設計する必要もあります。たとえば、技術記事の最後に「この技術を活用した事例を見る」といった導入事例へのリンクを設けたり、製品ページのなかに資料請求ボタンを視認性の高い位置に配置したりすることで、閲覧から入力までの行動をスムーズに誘導しやすいでしょう。
フォーム設計においては、会社名や部署名、現在の課題、導入検討時期といった営業活動に活かせる情報を収集できるようにするのが理想です。ただし、入力項目が多すぎると離脱の原因になるため、必要最低限の情報に絞り、「この程度であれな入力してもいい」と思ってもらえる設計がポイントです。
なお、取得した情報はCRMやMAに登録し、行動履歴も含めて一元管理することがおすすめです。
製造業におすすめの集客施策
製造業が集客を実施するにあたり、どのような施策が効果的なのでしょうか。「集客をしたいけれど何をしたらいいのか分からない」「製造業が実施できる施策が何なのか分からない」などの悩みを抱えている方は、以下の集客施策を参考にしてみてください。
SEO対策を実施する
製造業が集客を実施するにあたり、まず重要といえるのがSEO対策です。
たとえば、「ステンレス 溶接 歪み 対策」「省スペース 加工機」など、技術的な課題や業務上の悩みで検索するユーザーが多いため、ニーズに応えるコンテンツを用意することが重要です。
技術ブログやコラムでは、現場でのトラブル事例や解決策、独自ノウハウなどをわかりやすく紹介し、専門性をアピールしましょう。
なお、製品名だけでなく、用途や業種、導入効果を想起させるキーワードを選ぶことも重要です。「穴あけ 精度 課題」「バリ取り 自動化 装置」などのキーワードでコンテンツを制作し、Google検索で上位表示されるページを増やしていくことで、リード獲得数も向上できます。

業界に特化したメディアに情報を掲載する
製造業向けの業界特化メディアに情報を掲載することで、狙いたい業界や職種に対して効率的にアプローチできます。
「品質管理者向け」「開発担当者向け」といったターゲット像を想定し、訴求内容やタイトル、資料内容を統一させることで、読み手の関心を引きやすくなるでしょう。
とくに、IPROSや現場改善系メディアのように専門性の高い媒体では、信頼性のある情報として扱われるため、資料請求やお問い合わせなどの行動にもつながりやすくなります。
Web広告に出稿する
短期間でたくさんのリードを獲得したい場合には、Web広告を活用する方法がおすすめです。業界専門メディアの広告枠やGoogle検索広告、バナー広告など、製造業が選べる媒体は多いため、目的に合わせて取り入れましょう。
Web広告の出稿で特におすすめのケースであるのが、新製品をリリースする際や展示会出展前などです。広告は出稿期間に限りがあるため、時期を絞って強く訴求する際に便利です。
とはいえ、Web広告は出稿して終わりではありません。リードの獲得につながるか否かは、「クリック後のコンテンツ内容」によって決まります。問い合わせや資料請求につながるランディングページを用意し、CTAを設計しておくことが重要です。
また、Web広告を出稿したままにするのではなく、運用中のアクセス分析やPDCAサイクルを回していく必要があります。費用対効果を高めるためにも、効果測定も視野に入れた運用体制を構築しましょう。
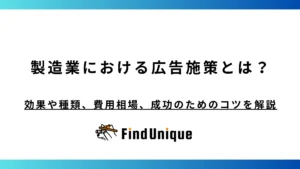
製造業におすすめのリード化コンテンツ
製造業がリード獲得を目指すにあたり、重要なのが「コンテンツ」です。リード化しやすいコンテンツとしては、以下が挙げられます。
- ホワイトペーパー・技術資料を配布する
- 事例紹介・お客様の声を公開する
- ウェビナーを開催する
- 製品カタログを配布する
それぞれのコンテンツについて、詳しく解説していきます。
ホワイトペーパー・技術資料を配布する
製造業におすすめのリード化コンテンツとして、まず挙げられるのがホワイトペーパーや技術資料です。
製造業では、技術力や知見の深さが信頼獲得につながります。ホワイトペーパーは、製品カタログとは異なり、「課題と解決策」「導入ステップ」「業界トレンド」など、読者にとって実務に役立つ知識を提供できる資料です。
たとえば、「バリ取り自動化の成功事例3選」や「ステンレス溶接における歪み対策ガイド」など、課題をもとに設計された資料が有効でしょう。ダウンロード資料として提供し、フォーム入力時に会社名・部署・連絡先などの情報を得ることで、リードが獲得できます。
また、営業が訪問する前に資料を読んでもらうことで、信頼の土台を築いた状態で商談ができるため、提案の成功率も向上するでしょう。
なお、製品カタログもリード獲得におけるコンテンツとして必須です。しかし、「ただのスペック表」にならないように工夫しなければなりません。
サイズや対応素材を羅列するだけではなく、「○○な使い方ができます」「導入前に確認すべき3つのポイント」など、導入シーンを想像させる情報を加えることで、見込み顧客の興味を引く内容になります。
製品カタログを準備する際は、紙とWebの両方を準備しておきましょう。紙のカタログは展示会での配布や営業訪問時に活用し、PDF版はWebサイトの資料請求ページからダウンロードできるようにすることでオンライン・オフラインでリード獲得チャンスを高められます。
事例紹介・お客様の声を公開する
導入事例やお客様インタビューは、技術者・上長・購買担当のすべてに響く万能なコンテンツといっても過言ではありません。「自社が導入した場合」をイメージしやすく、現状との比較や課題の解決方法を想像することにつながるからです。
とくに、「〇〇業界で導入後に不良率が30%削減された」「△△製造ラインの人手を2名分削減」など、数字で根拠をアピールできると、説得力も増し、ユーザーの購買意欲も向上できます。
事例やお客様の声を公開するのであれば、導入前の課題から選定理由、導入後の効果といった流れのストーリー形式がおすすめです。ユーザーが自社の課題と重ね合わせやすくなり、導入後について「具体的にどう役立つか」がイメージしやすくなり、結果的に導入を前向きに検討してもらえる可能性が高まります。
ウェビナーを開催する
ウェビナーは、オンラインでリード獲得と信頼構築を同時に行える施策です。たとえば「AI画像検査の活用と誤検出対策」や「◯◯工程の自動化に成功した企業の実例」など、関心度の高いテーマを選べば、業界外からも参加者が集まりやすくなります。製品や技術の魅力を直接伝えられるため、競合との差別化にもつながる機会といえるでしょう。
申し込みフォームで取得した情報(業種や職種、検討時期等)を活用すれば、セミナー後の個別フォローも可能です。
ウェビナーでは、セミナー中にチャットで質問を受ける形式にすることもおすすめです。見込み顧客の悩みや課題を把握する機会になるため、製品のブラッシュアップや自社の強みの訴求方法の参考につなげられるでしょう。
Webサイトをリニューアルする
「製品情報は載っているが、問い合わせにつながらない」といった課題がある場合には、Webサイトをリニューアルしましょう。とくに、製品のスペックを中心に公開しているWebサイトの場合、ユーザーに自社の強みや実績などが伝わっていない可能性があります。
Webサイトを見直す際には、製品のスペックだけでなく「なぜ自社を選ぶべきか(強み・実績)」を打ち出せているかをきちんとチェックしてみてください。
導入事例や対応スピード、サポート体制など、競合との差別化要素をファーストビューで伝える構成にすることで、離脱を防ぎつつ効果的にアピールできます。
また、CTA(問い合わせボタン・資料請求フォーム)を目立つ位置に配置し、スマホからでも快適に操作できるようレスポンシブ対応を徹底します。情報の「見つけやすさ」「読みやすさ」を意識しましょう。

リードを獲得した後に必要な育成・教育(ナーチャリング)
製造業が必要なのは、リード獲得だけではなく「獲得したリードをどうするか」です。商談化のステップへと進めるためにも、獲得したリードは以下のように育成・教育していく必要があります。
- マーケティングオートメーションを活用する
- メルマガを配信する
- ウェビナーを開催する(リード獲得後も定期的に)
それぞれ、どのような育成・教育となるのか、以下から見ていきましょう。
メルマガを配信する
メルマガ配信は、獲得したリードとの接点を定期的に得られる施策です。主に「月1回の技術コラム」「導入事例紹介」「展示会出展情報」などをメルマガで継続して配信することで、見込み顧客に「忘れられない」関係を維持できます。
定期的なメルマガ配信で、「技術力の高い会社」「業界の動向に詳しい企業」という印象を与え、信頼感を醸成できるため、見込み顧客の検討期間が長い製造業にとって必要な施策です。
メルマガの開封率や、クリック率を分析して、見込み顧客が関心を寄せているポイントも把握し、次回のセミナー案内や個別営業のタイミングを図っていきましょう。
ちなみに、メルマガを運用するのであれば、マーケティングオートメーションの活用がおすすめです。マーケティングオートメーションであれば、見込み顧客の情報を管理したり、アプローチや育成を自動化・効率化することが可能です。
開封やクリック、ページ閲覧などの行動にスコアをつけたうえで「商談につながりやすいホットリード」として、営業と連携することもできるため、営業活動の効率化にもつながるでしょう。

ウェビナーを開催する(リード獲得後も定期的に)
リード獲得を目的として実施されることの多いウェビナーは、ナーチャリングの施策としても活用できます。
「最新技術の活用法」「失敗しない設備選定のポイント」など、参加者の関心度を高めるテーマで定期的に開催することで、定期的な接点を持てるだけでなく、導入の検討を前向きに考えてもらいやすくなるでしょう。
ただし、ウェビナーは開催後のフォローも必要です。「お礼メールの送信」「補足資料の提供」「個別相談のご案内」などを行うことで、参加者との関係性がより深まり、商談化率が大きく高まります。
製造業のリード獲得ならファインドユニーク
製造業におけるリード獲得は、単なるWebサイトのアクセス増や展示会での名刺収集にとどまらず、「誰に・何を・どう届けるか」という戦略設計と、ナーチャリングが欠かせません。
とはいえ、SEO、広告、ホワイトペーパー、ウェビナー、MAツールの運用など、やるべきことが多く、社内に専任人材がいないケースも珍しくありません。
そんなときには、製造業に特化したマーケティング企業「ファインドユニーク」にご相談ください。
ファインドユニークでは、製造業特有の課題をふまえた解決策を一緒に模索していきます。
リード獲得に悩む製造業マーケティング担当者の方は、まずは一度お気軽にご相談ください。

本資料は、製造業がこれからの時代に必要とされる「Webマーケティングを取り入れた営業の仕組み」について解説しております。
どのようにWebマーケティングを自社の営業活動に取り入れていくかを具体的に解説しております。ぜひ参考にしてください。